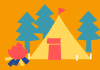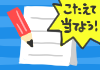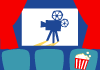赤ちゃんが口にする食材のうち、注意が必要なものの代表として「牛乳」があげられます。与える時期として「1歳から」がひとつの目安となっていますが、それにはさまざまな理由があるようです。そこで、お茶の水女子大学教授であり、小児科医の榊原洋一先生にお話を伺いました。
母乳と牛乳では、含まれる栄養素の「濃度」が違う

母乳と牛乳はどちらも白い液体で、一見同じように見えますが、含まれる成分には違いがあると榊原先生。
「牛乳は牛の赤ちゃんの成長に、母乳は人間の赤ちゃんの成長を促すために必要な成分がそれぞれ含まれています。栄養素ごとに見ていくと、たんぱく質やミネラルは母乳よりも牛乳のほうが濃い。逆に、糖質は牛乳よりも母乳のほうに多く含まれているのです。」
「牛乳と母乳の成分が違う理由は、牛の赤ちゃんと人間の赤ちゃんの成長発達に関係しています。まず、牛と人間では育つスピードが違います。牛のほうが、体が大きく人間よりも成長が早いため、体の形成に必要なたんぱく質やミネラルをより多く消費します。」
「逆に、体の成長速度に対し脳が早く発達するのは人間のほう。脳の占める割合は牛よりも人間がより大きいことから、人間の赤ちゃんは、脳の発達に必要な糖分を多く体内に取り入れていきます。そのため、人間の赤ちゃんが摂取する母乳には、“乳糖”という糖分が多く含まれているというわけです。」
見た目は同じでも、成分はそれぞれの赤ちゃんの成長に合うように、自然と調整されているのですね。
母乳の代わりに牛乳を与えてはいけない理由とは?

このように母乳とは成分が異なる牛乳を飲むと、赤ちゃんの体にどんなデメリットがあるのでしょうか?
「まず、牛乳に多く含まれるたんぱく質やミネラルを過剰に摂取すると、腎臓に負担がかかってしまいます。また、牛乳には母乳に多く含まれる乳糖があまり含まれていないので、赤ちゃんの成長に影響がでてしまいます。」
「さらに、牛乳には鉄分の吸収を抑える成分が含まれているため、牛乳のみを摂取し続けると、体内の鉄分が欠乏する『牛乳貧血』という状態を引き起こしてしまうこともあります。」
そのため、牛乳を母乳の代用とすることはできず、母乳からほとんどの栄養をまかなっている0歳の赤ちゃんは牛乳を摂取しないほうがいいとされているそう。
「母乳の代用としては、成分の近い粉ミルクが一般的に使われています。粉ミルクは、母乳に含まれる免疫は含まれていないものの、その成分は限りなく母乳に近いものです。そうしたことからも、0歳児においては、母乳の代わりに粉ミルクを飲ませるのがよいとされています。」
「ただし、災害時に粉ミルクやお湯が手に入らないという状況においては、急場しのぎとして牛乳を与えても構いません。一時的なことでしたら命に危険を及ぼすものではありませんので、まずは飢えをしのぐことを優先させましょう。」
「牛乳は1歳を過ぎてから」はなぜ?
厚生労働省が策定した『授乳・離乳の支援ガイド』によると、「牛乳の飲用は1歳を過ぎてから」とあります。なぜ0歳はダメなのに、1歳を過ぎれば牛乳を飲んでも大丈夫なのでしょうか?
「大人は、エネルギーとして食事を摂取していきますが、0歳の赤ちゃんにとっての食物は体を作る材料そのもの。なにせ、1年で体重が出生時の3倍、身長が1.5倍にも増えるのですから。そのため、大人が何気なく摂取しているものでも、赤ちゃんの成長発達には非常に大きな影響を与えるのです。」
生まれた直後は100%母乳や粉ミルクからの栄養に依存している赤ちゃんですが、一般的に生後5カ月〜6カ月頃の離乳食開始時で80%〜90%、3回食に移行する9カ月〜11カ月頃でも30%〜40%と、成長に伴い徐々に離乳食から摂る栄養分が増えているといわれています。
「1歳を過ぎると離乳食が完了し、さまざまな食品を摂取できる段階に移行するため、牛乳のみでは補いきれない栄養素をご飯や肉、魚などからも摂取できるようになります。」
この頃になると、食事から摂る栄養が80%〜85%まで増え、牛乳を摂取することでの栄養面での影響が少なくなります。これが1歳を牛乳解禁の目安としている大きな理由のようです。
牛乳を飲ませるときに注意することは?

1歳を過ぎてから牛乳を飲ませるときに、気をつけるポイントはありますか。
「牛乳も他の食品と同じように、最初は少量から与えはじめてください。調理して離乳食のメニューに加えていきながら、段階を経て直接飲ませていくとよいでしょう。」
「最初に飲ませるときは、母乳の状態に近い人肌程度に温め、体調やうんちの状態に問題がなければ常温に戻したものを、様子を見てさらに問題がなければ、次の段階として冷たい牛乳を与えるようにします。最初はひとさじから。様子を見ながら、徐々に量を増やしていってください。」
子どもの様子をよく確認しながら、徐々に牛乳をメニューに加えていくということが大切なのですね。赤ちゃんにとって影響が大きな食材「牛乳」。しっかりとした知識を身につけたうえで、体に負担がないように与えてあげたいものですね。