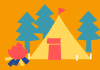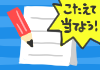子供との密着度が高く、家事など作業をするときにも安心な「おんぶ」。実は、おんぶが子供の発達にもいいというのをご存知でしょうか? おんぶのメリットについて、保育士として37年間幼児体育の研究を行ってきた中島澄枝先生に話を伺いました。
●ママにも優しい 赤ちゃんに負担が少ない抱っこの仕方子供の成長につながる「おんぶ」の3大メリット

おんぶをすることには、どんなメリットがあるのでしょうか?
「おんぶをすることで赤ちゃんの脳が育まれ、社会性が身に付き、身体能力の向上にもつながります」と中島先生。先生によると、おんぶには主に3つのメリットがあるといいます。
1. 視界が広がることで、脳に刺激を与える
「人間には視覚、聴覚、触覚などの感覚があります。その中でも最も大事なのは視覚。視覚はそのほかの感覚より早く、生後8カ月に成熟のピーク(視覚脳のシナップス臨界期)を迎えるのです。
人は外部から得る情報のうち、およそ8割を視覚で得ています。おんぶの場合、赤ちゃんはパパ・ママの肩越しに周りを見渡すことができます。そのため赤ちゃんの視野がいつもより広がり、脳への刺激を十分に与えられます。
大人と同じ目線になるおんぶは、赤ちゃんにとっていつもとは違うものが見える新鮮で楽しい時間。なので、知的好奇心を育むことができます」
2. パパとママと同じ視点で疑似体験をして学べる
「おんぶをすると赤ちゃんはパパやママが行っていることを、あたかも自分自身が行っているように感じられます。脳科学ではこの現象をミラーニューロンと呼び、他人の心と共感したり、社会性を養うことにもつながります」
3. 姿勢やバランス感覚を育む
「日本人は800年もの間『1本の紐でするおんぶ』を伝えてきました。これは世界で唯一の育児法で、この方法では比較的自由に赤ちゃん自身がポジションを変えられます。
ポジションが変えられることで、赤ちゃんは普段とは違った景色を見ようと、自らの両腕で両親の背中にしがみつき、腰を伸ばして立ちあがろうとします。
赤ちゃんがあちこちにしがみつくことで、体幹が自然と鍛えられ、バランス感覚が向上します。さらに、お座りから立つことへの練習や姿勢のよい体作りにつながっていきます」
何気ないおんぶが子供の視野を広げて脳への刺激やさまざまな発達につながるのですね。赤ちゃんのうちに積極的におんぶをしてあげましょう。
おんぶは忙しいママにもおすすめ

夕方の一番忙しい時期に限って、赤ちゃんが泣き出すというのもよくある話。ついついテレビやDVDを見せてしまいがちですが、これは赤ちゃんの脳には刺激過多。そういうときこそおんぶがオススメだそう。
「赤ちゃんを抱っこ、おんぶする機会が多い保育園の先生たちが愛用しているのはおんぶ紐。おんぶをすると両手が自由になるので、お母さんの場合は家事などの作業もしやすいです。子供をうしろに背負うことで、足元の視界をしっかり確保でき、動きやすいのもメリットですね。災害時の逃げるときなどにも有効です」
とくに火を使う、包丁を使うなど、炊事をするときは、子供の手が前方に届かないおんぶの方が安心ですよね。また、ぐずっていて早く寝かしつけたいときも、おんぶが有効です。外に出てゆったりと散歩すると、大人の歩く振動がリズムになってすぐに眠りについてくれます。
「おんぶは抱っこよりも肉体的負担がラクに感じます。例えば、登山をするときは荷物を高い位置に背負っていますよね。これは背負う方が、荷物の重さを体の中心で支えられるからです。さらに背負う際に必要な筋肉は、抱っこをする際に使う筋肉よりも強いため、人の体型は重い物を持つときは背負うように設計されているのです」
「また、重い荷物を持つとき、体から離れた位置で持つと、より重さを感じてしまいます。その点、おんぶはママ・パパと赤ちゃんの背骨のラインがきれいに沿うようになるので、背中にぴったりフィットして重さを感じにくいのです」
忙しいママこそ家事や寝かしつけなど、おんぶをうまく活用したいですね。
おんぶするときの注意点とは?
一方、おんぶをする際の注意点はあるのでしょうか?
「おんぶの開始時期は、首が座る生後4カ月頃からが目安。おんぶ紐の種類によって異なる場合があるので、必ず使用期間を確認しましょう。また、おんぶで重要なのは、赤ちゃんの顔の位置です。高い位置でお母さんの肩越しに前方が見えることができるおんぶ紐を選びましょう」
腰ベルトタイプの抱っこひもの場合、腰の位置でベルトを巻きつけるため、赤ちゃんの視界が背中で遮られてしまい、狭い視界になってしまいます。そのため、できれば昔ながらの1本の紐でおんぶする方法がベスト、と中島先生。
「その場合は、最初は誰かに手伝ってもらうか、ソファに赤ちゃんをもたれかけさせ、大人が床に座った状態で背負うとよいでしょう。60代〜70代の女性ならできる方が多いので、声をかけて教えを乞うのも一案です」
「目の届かない背中に赤ちゃんを回すのが不安な方は、右手で赤ちゃんの脇を通した2本の紐をしっかり持ちましょう。背中に乗せた状態で、この右手の紐を緩めなければ落ちません」
おんぶのやり方や身だしなみにも配慮を
「赤ちゃんは股関節がM型でよく開くものですが、近年股関節が開かない子を見かけます。床でのハイハイを親指で蹴って進まない子の多くは脚が開きません。こういう赤ちゃんの場合は、おんぶしたら脚をお母さんの身体にまきつくように前に出してあげてください」
また、おんぶをする際はお母さんの身だしなみにも気をつけましょう。
「子供が肩越しにお母さんのしていることや広い世界を見渡す伝承のおんぶは、お母さんの髪の毛が長いと、子供の目や鼻に当たって衛生的ではありません。束ねてアップするか、帽子などで髪が子供の顔に触れないようにしてください」
おんぶをすると、早いと1カ月でおんぶをした時の赤ちゃんの顔つきがパッと明るく変わっていくそう。ママとパパ、そして赤ちゃんにメリットがあるおんぶ。まだしたことがない人は、ぜひ挑戦してみてください。