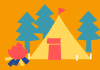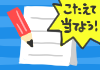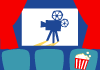「幼稚園教育要領」「保育所保育指針」「幼保連携型認定こども園教育・保育要領」の3つを合わせた通称「3法令」が、2017年3月に大きく改正し、2018年の4月から施行されています。子育て世帯にとっては関心の高い話題ですが、「実際に何がどう変わったのかよくわからない」という人も多いのでは?
そこで今回は、「保育総合研究会」副会長の坂崎隆浩さんに3法令改正のポイントを教えてもらいました。
法令改正の背景や目的は?

「幼稚園教育要領」「保育所保育指針」「幼保連携型認定こども園教育・保育要領」の3つを合わせた「3法令」は、幼稚園・保育園・認定こども園のそれぞれが目指すべきところを定めたもの。今回は、どのような目的で改正されたのでしょうか。
「10年前まで1歳〜2歳の子どもの入園率は20%台でしたが、2017年には40%台になりました。家庭ではなく施設での保育が一般的になる時代がもうすぐやってきます。また、これからの時代を生き抜く力を培う基礎とともに、幼児教育の大切さが認識されてきています」
「そこで、3つの施設のいずれも『豊かな環境で安心・安全に育ち、小学校入学以降につながる質の高い教育が受けられる幼児教育施設』である必要があるとし、そのために法令を見直したのが今回の改正です。これまで幼稚園は『教育課程』、保育所は『保育課程』に基づいた教育や保育を行っていましたが、どちらも認定こども園と同じく『全体的な計画』を作ることになりました」
「幼稚園=教育」「保育所=福祉」「認定こども園=その中間」というイメージがありますが、今回の改正で3つの施設がお互いに近いものになったそう。いわゆる「保育園育ち」「幼稚園育ち」といった区別もなくなるかもしれません。ただし、幼児教育といっても読み書きや計算などを早いうちから教えるという意味ではありません。
3施設共通の目標は?

では、具体的にどういった目標や狙いがあるのでしょうか。
「今回の改正で、3つの施設すべてが『幼児教育機関』に位置づけられたことで、3つの施設が目指す目標も同じになりました。幼稚園、保育所、認定こども園の共通の目標として定められた『3つの柱』と『幼児期の終わりまでに育ってほしい10の姿』を紹介します」
教育の中で育みたい「3つの柱」
- 豊かな体験を通して、感じたり、気づいたり、わかったり、できるようになったりする「知識および技能の基礎」
- 気づいたことやできるようになったことなどを使い、考えたり、試したり、工夫したり表現したりする「思考力、判断力、表現力等の基礎」
- さまざまなことに意欲を持って粘り強く取り組み、目標に向かって努力できる力や、思いやりや安定した心を持つ「学びに向かう力、人間性等」
幼児期の終わりまでに育ってほしい10の姿
- 健康な心と体
- 自立心
- 協同性
- 道徳性・規範意識の芽生え
- 社会生活との関わり
- 思考力の芽生え
- 自然との関わり・生命尊重
- 数量や図形、標識や文字などへの関心・感覚
- 言葉による伝え合い
- 豊かな感性と表現
「これらは、すべてを入学前に達成するという意味でも、子ども自身が生活を変えるという意味でもありません。『小学校との連携や接続も含めて、子どもがこのような姿に育つことができる環境を(施設が)提供する』と考えてください。このほか、家庭や地域に目を向けた子育て支援や、災害への対応も求められるようになりました」
それぞれで変化したポイント

では、3つの施設それぞれを見ると、どのような点が変わったのでしょうか。
一番大きく変わったのは「保育所」
「一番大きく変わったのが保育所です。0歳〜就学直前まで幅広い子どもの健康や安全を守る『養護』と『教育』を合わせた『保育』が行われていますが、今回、3歳未満児の教育に関わる部分についても詳細に決められました。細かいところまで規定されたのは今回が初で、職員の資質向上に関する内容も加わりました」
<具体的な変更点>
・1歳未満/1歳以上3歳未満/3歳以上に分け、それぞれの年齢の発達に合わせた養護と教育について規定
・教育に関する部分が幼稚園・認定こども園とまったく同じに
・職員のスキル&キャリアアップのための研修や職場環境の整備などを義務化
今回の改正により規定がしっかりと明文化されたことで、園ごとの差がなくなることが一番のポイントといえそうですね。
教育を大切に、それ以外の充実も求められる「幼稚園」
「もともと、日本中で同じ水準の教育が受けられるという教育課程のもとで運営されている幼稚園では、教育内容に関して大きな変化はありません」
「今回新たに加わったのは、『教育時間』として定められている4時間以外(預かり保育)や、家庭における子どもの生活に配慮しようというもの。預かり保育の内容を充実させることや、家庭での過ごし方について、専門家としてアドバイスをすることなどが含まれます。なお、今後の望まれる子ども像は、教育要領の前文に書かれています。幼稚園にも置いてあるので、ぜひお読みください」
<具体的な変更点>
・預かり保育や子育て支援などの工夫
・地域の教育センターとしての役割
”教育のプロ"として、子どもの1日の流れまで考えたサポートやアドバイスといった役割が期待されそうですね。
地域での役割が増す「認定こども園」
「誕生からわずか10年あまりの認定こども園は、2015年に『子ども・子育て支援新制度』が施行されたばかりということもあって、今回改正された箇所が一番少ない施設です。『全体的な計画』も『教育課程』もすでにありました」
「保育所と同様に、さまざまな年齢に応じた保育が求められるとともに、一時預かり事業や地域の人材を活用した子育て支援など、地域の教育や児童福祉に関する総合的な施設としての役割が、ますます求められるようになりました」
<具体的な変更点>
・「1歳未満/1歳以上」「3歳未満/3歳以上」に分け、それぞれの年齢の発達に合わせた養護と教育について規定
・地域の子育て世帯に対する支援の充実
もともと、幼稚園と保育園のよいところを取り入れている認定こども園。地域との関わりが増えればいっそう頼れる施設になりそうです。
幼児が通うすべての施設のレベルアップが目的ともいえる今回の改正。坂崎さんによると、保護者や子どもが生活を変える必要はないそうですが、頭に入れておきたいですね。