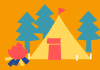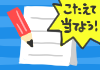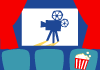子ども向け運動教室からプロアスリートの指導までを手掛けるフィジカルアドバイザー廣戸聡一さん。「苦手だなぁ」と思っている子も多い、ボール投げ、かけっこ、逆上がりの上達のコツをお聞きしました。その答えは、テクニックよりもっと手前にある基本的なことでした。
 廣戸聡一さんが開催するボール投げ教室では、2時間の授業のうち1時間50分は「ボールも使わずただ遊んでいるだけ」なのだそうです。
廣戸聡一さんが開催するボール投げ教室では、2時間の授業のうち1時間50分は「ボールも使わずただ遊んでいるだけ」なのだそうです。
「そこにタッチして戻ってきて」「間に置いてあるイスに座って」といったタスクを子どもに与え、みんなで元気に動き回ります。終了10分前、廣戸さんがカゴいっぱいのボールを持ってきたと思ったら、すってんころりん。ボールをぶちまけてしまいます。子どもたちは大はしゃぎ。
「ボールをこのカゴに入れて」と廣戸さんが声をかけると、子どもたちはボールをポンポンとカゴに投げ入れます。「子どもたちは上手に投げようなんて考えていません。みんな、ただ遊んでくれたこの人にボールを入れてあげようと思っているだけ。テクニックではありません」。
ボール投げには、以下の段階があります。
一人称的…投げる
二人称的…ここに投げる
三人称的…何の(誰の)ために、ここから受け取ったものを、ここに投げる
この三人称的の部分がコミュニケーションです。
「おもしろいよ、とプレーの目的や目標を与えてあげることが大事。目的意識があると、人は自然な動きをするようになります。フォーム重視というのは、肉体労働しているのと同じ。蹴ったり転がしたりしながら、一緒にボールでいっぱい遊んでみてください」。
 相手がいるボール投げと違って「かけっこ」は個人種目のように思われますが、やはりコミュニケーション能力がカギになると廣戸さん。
相手がいるボール投げと違って「かけっこ」は個人種目のように思われますが、やはりコミュニケーション能力がカギになると廣戸さん。
「陸上競技も、駆け引きが必要です。走るのが速い子どもは、走ることに興味を持った子。誰よりも速くゴールにたどりつきたいと思い、スタートダッシュで飛び出していく。一方、走れと言われたから一応走っているだけの子もいます。そういう子はキョロキョロしたりして、『がんばれ』と言ったお母さんのほうに走ってきたりする。それは、走ることよりもお母さんが好き、それだけなんです。」
人間は、誰が教えなくても立ち、歩き、走ることを始めます。こうした「赤ちゃんが始める動き」は、ほぼ正しい動きだと廣戸さんは言います。
「走り方や歩き方をはじめから教えようとしないでください。一人ひとり走り方は違いますし、フォームが不格好のようでも速い子もいます。子どもが走っている様子をよく観察してください。どうしても気になることが見えてきたら、『こうしてみたら』と一言だけ言ってみる。テクニックを説明するのではなく、お母さんの言う通りにすれば速く走れる!と子どもに思ってもらうことが一番です。」
 ボール投げもかけっこも、子ども自身の「そこに投げたい」「速くたどりつきたい」といった目的意識が必要、というお話でした。その意識を親が引き出すには、一緒に体を動かし、子どもをよく観察しようと廣戸さんは呼びかけます。
ボール投げもかけっこも、子ども自身の「そこに投げたい」「速くたどりつきたい」といった目的意識が必要、というお話でした。その意識を親が引き出すには、一緒に体を動かし、子どもをよく観察しようと廣戸さんは呼びかけます。
では鉄棒で逆上がりをする際、子ども自身にやる気があって一生懸命練習するも一向にできるようにならない場合は…? 筆者の子どももその一人。腕が伸びきっている、お尻が持ち上がらないなど問題点は明らかですが、どうしたものでしょう。
「鉄棒の前哨戦をやっていますか」と廣戸さん。「逆上がりは難しいんです。手だけじゃない、体を使って鉄棒をホールドし、ジャンプして、瞬発力で体を回し、初めてお尻を上げられる。体が不安定な状態でも恐怖心がないことも大事です。お父さんの体に全身の力でしがみついてゴロゴロ転がされたり、でんぐり返しをしてゲラゲラ笑っていられるといった経験が生きてきます。」
なるほど、日頃の遊び(じゃれ合い)で身につけた身体能力の結集とも言える逆上がり。ひたすら黙々と鉄棒と対面して逆上がりを練習することは、上達の近道ではなさそうです。
廣戸さんは、「競技者にさせすぎないで」と訴えかけます。「いろいろなスポーツをやらせたほうが運動能力は上がります。人には伸び時があります。その子の最も自然に能力が発揮できる可能性をみつけてあげてほしいです。それを自分で発見させてあげること。好きなことを自分で見つけたらその子は強い。どんどん伸びていきます。」
わが子は小学生になり、一緒に体を動かして遊ぶ時期は卒業かなと思っていましたが、まだまだこれからなのかもしれません。時々一緒に公園を駆け回ったり、新しいスポーツを始めたりするのもおもしろそうだと思いました。逆上がりは…気長に、時々練習に付き合いつつ、くるっとできるようになる日を楽しみにしたいです。
運動の基本はコミュニケーション
ボールを使わないボール投げ教室!?
 廣戸聡一さんが開催するボール投げ教室では、2時間の授業のうち1時間50分は「ボールも使わずただ遊んでいるだけ」なのだそうです。
廣戸聡一さんが開催するボール投げ教室では、2時間の授業のうち1時間50分は「ボールも使わずただ遊んでいるだけ」なのだそうです。「そこにタッチして戻ってきて」「間に置いてあるイスに座って」といったタスクを子どもに与え、みんなで元気に動き回ります。終了10分前、廣戸さんがカゴいっぱいのボールを持ってきたと思ったら、すってんころりん。ボールをぶちまけてしまいます。子どもたちは大はしゃぎ。
「ボールをこのカゴに入れて」と廣戸さんが声をかけると、子どもたちはボールをポンポンとカゴに投げ入れます。「子どもたちは上手に投げようなんて考えていません。みんな、ただ遊んでくれたこの人にボールを入れてあげようと思っているだけ。テクニックではありません」。
テクニックを教えてもうまくならない
上の例に見られるように、「運動の基本はコミュニケーション能力」と廣戸さんは言いきります。「コミュニケーション能力とは、人付き合いがうまいということではありません。状況判断ができる、目的意識があるということ。今何をすべきかを把握し、適切に動くことです」。ボール投げには、以下の段階があります。
一人称的…投げる
二人称的…ここに投げる
三人称的…何の(誰の)ために、ここから受け取ったものを、ここに投げる
この三人称的の部分がコミュニケーションです。
「おもしろいよ、とプレーの目的や目標を与えてあげることが大事。目的意識があると、人は自然な動きをするようになります。フォーム重視というのは、肉体労働しているのと同じ。蹴ったり転がしたりしながら、一緒にボールでいっぱい遊んでみてください」。
足が速い子と遅い子の違いは
子どもの「自然な走り」を観察しよう
 相手がいるボール投げと違って「かけっこ」は個人種目のように思われますが、やはりコミュニケーション能力がカギになると廣戸さん。
相手がいるボール投げと違って「かけっこ」は個人種目のように思われますが、やはりコミュニケーション能力がカギになると廣戸さん。「陸上競技も、駆け引きが必要です。走るのが速い子どもは、走ることに興味を持った子。誰よりも速くゴールにたどりつきたいと思い、スタートダッシュで飛び出していく。一方、走れと言われたから一応走っているだけの子もいます。そういう子はキョロキョロしたりして、『がんばれ』と言ったお母さんのほうに走ってきたりする。それは、走ることよりもお母さんが好き、それだけなんです。」
人間は、誰が教えなくても立ち、歩き、走ることを始めます。こうした「赤ちゃんが始める動き」は、ほぼ正しい動きだと廣戸さんは言います。
「走り方や歩き方をはじめから教えようとしないでください。一人ひとり走り方は違いますし、フォームが不格好のようでも速い子もいます。子どもが走っている様子をよく観察してください。どうしても気になることが見えてきたら、『こうしてみたら』と一言だけ言ってみる。テクニックを説明するのではなく、お母さんの言う通りにすれば速く走れる!と子どもに思ってもらうことが一番です。」
逆上がりの前に「ゴロゴロ遊び」を
 ボール投げもかけっこも、子ども自身の「そこに投げたい」「速くたどりつきたい」といった目的意識が必要、というお話でした。その意識を親が引き出すには、一緒に体を動かし、子どもをよく観察しようと廣戸さんは呼びかけます。
ボール投げもかけっこも、子ども自身の「そこに投げたい」「速くたどりつきたい」といった目的意識が必要、というお話でした。その意識を親が引き出すには、一緒に体を動かし、子どもをよく観察しようと廣戸さんは呼びかけます。では鉄棒で逆上がりをする際、子ども自身にやる気があって一生懸命練習するも一向にできるようにならない場合は…? 筆者の子どももその一人。腕が伸びきっている、お尻が持ち上がらないなど問題点は明らかですが、どうしたものでしょう。
「鉄棒の前哨戦をやっていますか」と廣戸さん。「逆上がりは難しいんです。手だけじゃない、体を使って鉄棒をホールドし、ジャンプして、瞬発力で体を回し、初めてお尻を上げられる。体が不安定な状態でも恐怖心がないことも大事です。お父さんの体に全身の力でしがみついてゴロゴロ転がされたり、でんぐり返しをしてゲラゲラ笑っていられるといった経験が生きてきます。」
なるほど、日頃の遊び(じゃれ合い)で身につけた身体能力の結集とも言える逆上がり。ひたすら黙々と鉄棒と対面して逆上がりを練習することは、上達の近道ではなさそうです。
親子でいろいろなスポーツをしよう
好きなものを自分で発見する喜びを
「もっと歩こう、走ろう、転がろう」と声を大にする廣戸さん。「今は、『ドタバタしちゃダメ』『洋服が汚れるからダメ』と親が何もさせていません。それでいて、早い段階で一つのスポーツに特化して上を目指しすぎていると思います。」廣戸さんは、「競技者にさせすぎないで」と訴えかけます。「いろいろなスポーツをやらせたほうが運動能力は上がります。人には伸び時があります。その子の最も自然に能力が発揮できる可能性をみつけてあげてほしいです。それを自分で発見させてあげること。好きなことを自分で見つけたらその子は強い。どんどん伸びていきます。」
わが子は小学生になり、一緒に体を動かして遊ぶ時期は卒業かなと思っていましたが、まだまだこれからなのかもしれません。時々一緒に公園を駆け回ったり、新しいスポーツを始めたりするのもおもしろそうだと思いました。逆上がりは…気長に、時々練習に付き合いつつ、くるっとできるようになる日を楽しみにしたいです。