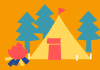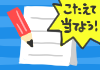子供が耳を痛がったり、詰まった感じがしたり、聞こえにくいなど、気になる症状があっても、親としてはどんな病気なのか判断しにくいですよね?
そこで今回、子供に多い耳の病気やトラブルについて、昭和大学医学部・耳鼻咽喉科学教室の主任教授の小林一女さんに聞きました。気付くポイントや家庭でできる予防法も紹介します。
耳の構造と「病気のなりやすさ」の関係は?

そもそも耳には音を聞く以外に、三半規管などバランスに関係する部分も含まれるのでしょうか。
「人の耳は、外耳・中耳・内耳の3つの構造に分けることができます。外耳は耳介(顔の横についている、いわゆる「耳」の部分)とそれに続く耳の穴(外耳道)までを言い、集音と音の伝達を担います」
「中耳はそのすぐ奥、鼓膜と耳小骨までの部分で、入ってきた音を受け止め、振動を内耳に伝える機能を持っています。内耳は、伝わった振動を電気信号に変えて脳に送る蝸牛(かぎゅう)と、身体のバランスを保つ三半規管からなっています」

子供は身体の構造上、大人より耳の病気になりやすいと聞きますが、本当でしょうか。
「子供の場合は、鼻の感染が耳にまで影響して炎症を起こすことが多いです。それは、耳と鼻をつなぐ耳管(じかん)と呼ばれるパイプが関係しています」
「大人の場合、耳管は鼻から耳に向かって、上がり坂になっていますが、子供は水平で、大人より太く短いため、鼻の感染が耳に影響しやすくなります。また、小さな子供ほど耳管の機能が未熟であることも、病気になりやすい原因かもしれません」
それ以外にも、耳をいじるなど、日常のちょっとした行動やクセが原因で起こるトラブルもあるようです。
子供に多い「耳の病気」や「トラブル」は?

では、具体的にどんな病気やトラブルが起こりやすいのでしょうか。
「圧倒的に子供に多いのは、『急性中耳炎』。『滲出性中耳炎』も重要です。『外耳炎』『耳垢栓塞(じこうせんそく)』は、どちらかといえば高齢者の方が多いですが、子供にも起こり得ます。珍しい疾患ですが、進行の過程で耳だれや難聴を起こす『先天性真珠腫(せんていせいしんじゅしゅ)』もあります」
急性中耳炎
中耳に炎症が起こり、耳の痛みや発熱、耳だれ(耳漏)、耳が詰まったような感覚などが生じる病気です。乳幼児がほとんどで、小学生以上になるとその頻度はぐっと減少します。
原因は鼻に感染した細菌・ウイルスが耳管を通じて中耳に及ぶためで、風邪や鼻炎に続いて起こることが多いです。
治療は、軽症なら最初の数日は経過観察。その後、症状に応じて抗菌薬などを使用します。症状がひどい場合は、最初から抗菌薬を投与することもあります。一週間程度で治ることがほとんどですが、治りきらずに耳に水が溜まるタイプの「滲出性中耳炎」や、再発を繰り返す「反復性中耳炎」に移行する場合もあるため、きちんと治療することが大切です。
滲出性中耳炎
中耳腔に水が溜まり、耳が聞こえにくくなるタイプの中耳炎です。多くは風邪や急性中耳炎に続いて発症します。乳幼児に多く、耳の痛みや発熱がないため、気づきにくいので注意が必要です。
呼びかけに返事をしない、聞き返すことが多い、テレビの音を大きくしたがる、言葉が遅かったり言い間違いをしたりと、「もしかして耳が聞こえにくいのかも?」と思うようなふるまいがあるときは気を付けましょう。
治療は、経過観察を中心に、状況により抗菌薬などを使います。大半は3カ月ほどで治りますが、それ以上経っても治らず、なおかつ両耳とも発症している場合は、中耳腔からの排水と通気のために鼓膜にチューブを入れることもあります(鼓膜換気チューブ留置術)。
外耳炎
外耳道に細菌などが感染することで引き起こされる急性感染症です。症状は耳の痛みや耳だれで、特に耳介(いわゆる「耳」の部分)を動かすと強く痛みます。耳の穴が腫れや分泌物の詰まりで狭くなっている場合、聞こえが悪くなることもあります。
原因は、外耳道の外傷や強い刺激です。子供の場合は、耳掃除や耳をいじるクセなどによって引き起こされることが多いようです。
治療は点耳薬が主ですが、抗菌薬を内服する場合もあります。耳掃除はなるべく行わないこと、耳が乾燥した状態を保つことが予防になります。
耳垢栓塞(じこうせんそく)
耳あかの塊によって外耳道が塞がれてしまう病気です。主な症状は聞こえの低下、耳の圧迫感、耳鳴りなどです。最もなりやすいのは高齢者ですが、子供に起こることもあります。
原因は耳に水が入って耳あかがふくらむことや、湿ったタイプの耳あかが出る体質であることなどです。補聴器を使っている方にも起こりやすいと言われています。
治療は耳あかを取り除くことですが、自分で行うのではなく、耳鼻科医を受診して取り除いてもらうことが重要です。
先天性真珠腫(せんていせいしんじゅしゅ)
生まれる前の段階で、本当は鼓膜の表面にあるはずの鼓膜の上皮成分の一部が奥の中耳に入り込み、大きくなってくるものを言います。
症状は、真珠腫が小さいうちは特に何もありませんが、大きくなってくると難聴や耳だれが生じます。より進行すると、中耳の周辺組織を壊してしまい、さまざまな悪影響を及ぼします。
真珠腫は、見つかったら手術で取り除くことが必要になります。検診や耳鼻科受診をきっかけに6歳くらいまでに見つかることが多いですが、気づかない場合もあります。小学生以上になっても中耳炎を繰り返す場合は注意が必要です。
耳の病気に気づくポイント&予防法は?

耳の病気やトラブルは、親も気付きにくく、子供もうまく説明できないことが多い傾向です。どんなことに注意すればいいでしょうか?
「子供のそぶりや行動を注意して見ることが大事です。赤ちゃんや小さな子供が、耳を引っ張ったり、しきりにこすったりして気にしている時は、痛みや不快な感覚があると思っていいでしょう」
子供の耳の病気を防ぐために、家庭で気を付けることはありますか?
「鼻の感染から中耳炎になることが多いため、まず、鼻のトラブルを防ぐことです。なるべく風邪をひかせないように注意し、鼻炎がある場合はきちんと治療しましょう。それから、耳掃除は耳を傷つけることもあるので、家庭で行うのはやめましょう。どうしても気になるときは、耳鼻科で掃除してもらうことをおすすめします」
小児科や歯科のかかりつけがあっても、耳鼻科のかかりつけがある方は意外に少ないのではないでしょうか。ぜひこの機に、定期的に受診する耳鼻科を探してみてくださいね。