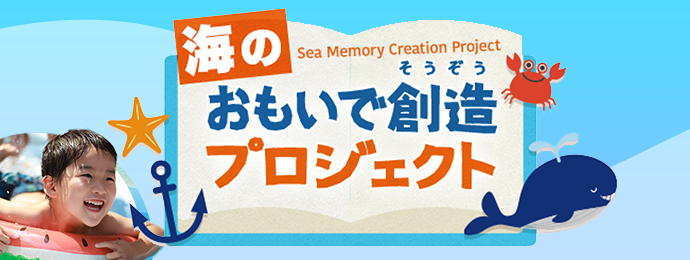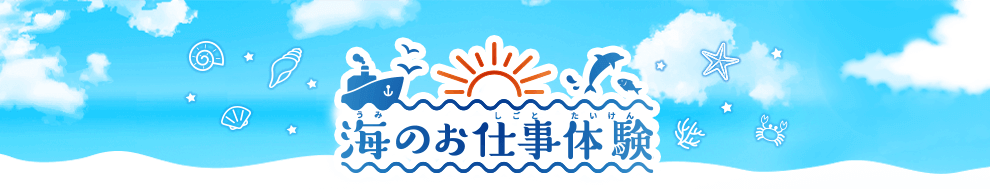
もっと知りたい!養殖業のお仕事

どんな種類の魚を養殖しているの?
マダイやブリ、クロマグロなどは天然物よりも養殖物のほうが多いと言われています。養殖のために使う魚や貝の子どもを「種苗」と言い、魚の種類によって種苗の作りやすさがちがうので、養殖がしやすい魚とそうでない魚があります。安定的によりたくさんの種類の魚を食べてもらえるよう研究が続けられています。魚以外にもアワビやホタテ、カキなどの貝類や、ノリやワカメなどの海そう類も養殖されています。
ブリ
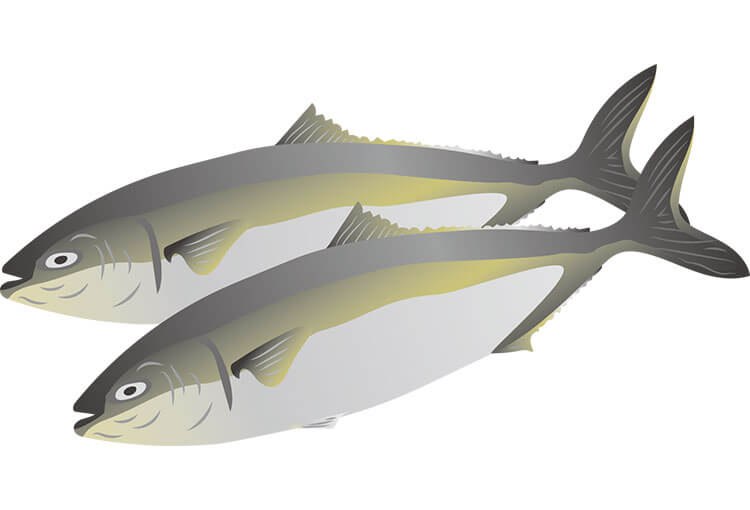
ブリは養殖業の生産量ナンバーワンの魚です。海水温18~27℃ほどの海で行われ、エサはイワシやアジなどの生魚や、栄養豊富なモイストペレットと呼ばれるものを使います。稚魚から約10か月ほどで重さ2~3kgに成長し、一回り大きいいけすに移った後で重さ5kgくらいになると全国に出荷されます。
マダイ
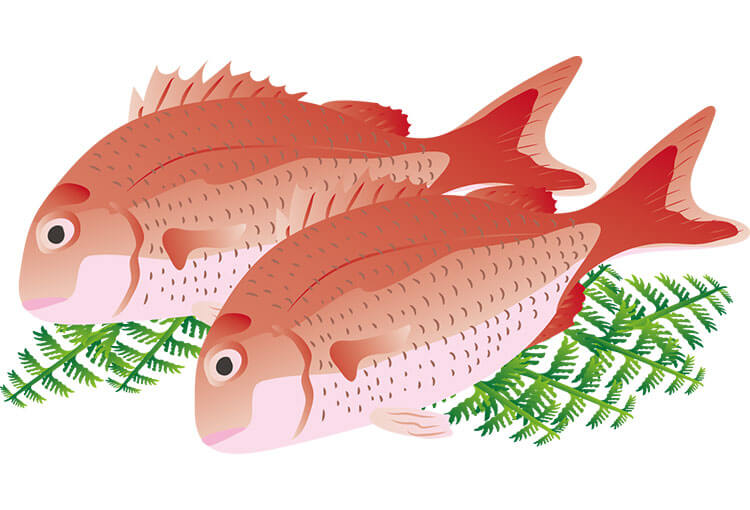
養殖用の種苗が手に入れやすいことから養殖がさかんにに行われ、生産量はブリについで国内2位です。お店にならぶようになるまでおよそ2年ほどかかります。マダイは長いあいだ太陽光を浴びると体が黒くなるため、いけすの上を黒いシートでおおうのが特徴です。
カンパチ

日本の南側のあたたかい海で多く養殖され、養殖生産量は第3位です。カンパチは水面より上に跳ぶことがあるので、いけすから飛び出さないように天井に網を張っておきます。また寄生虫がつきやすいため、いけすを清潔にしておく必要があります。出荷できるサイズの3キロ以上になるまでにおよそ2年かかります。
クロマグロ
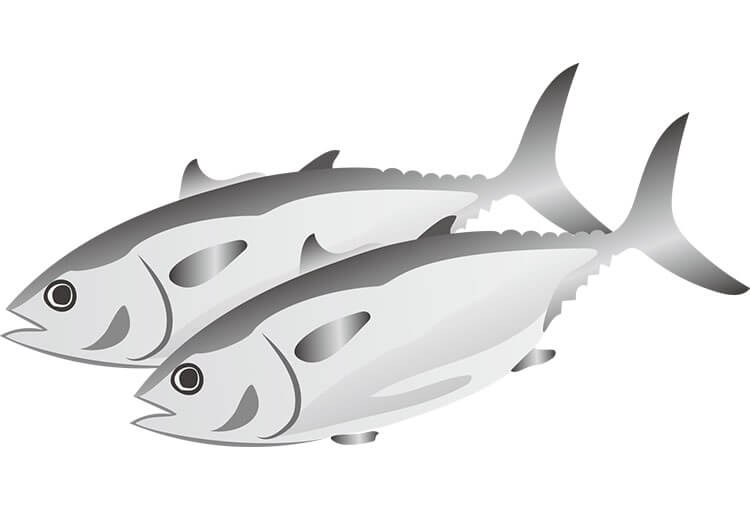
世界中で人気のマグロは、天然ものが少なくなっているため養殖が期待されています。体重100~500gのマグロの子どもを自然の海でつかまえて、2~3年かけて50kgくらいの大きさにまで育てます。他の魚は人工エサを使うことが多いですが、養殖マグロのエサのほとんどは生魚です。
トラフグ

海の中に網をはって育てる「海上養殖」と、陸地に水そうを作って育てる「陸上養殖」の2種類があります。5cmほどの大きさの赤ちゃんを、2年かけて1~1.5kgまで成長させます。フグのするどい歯でフグ同士が傷つかないように、一匹ずつ「歯切り」を行います。フグの養殖で一番大変な作業といわれています。
ヒラメ

ヒラメ養殖のほとんどが陸地でプールのような水そうで育てる「陸上養殖」で行われています。エサには栄養バランスのとれた人工エサを使い、赤ちゃんのころは1日3~4回エサやりをします。大きくなったら小さな生魚をあたえます。およそ1年半ほどで、お店にならぶ1kgぐらいのサイズになります。
クルマエビ
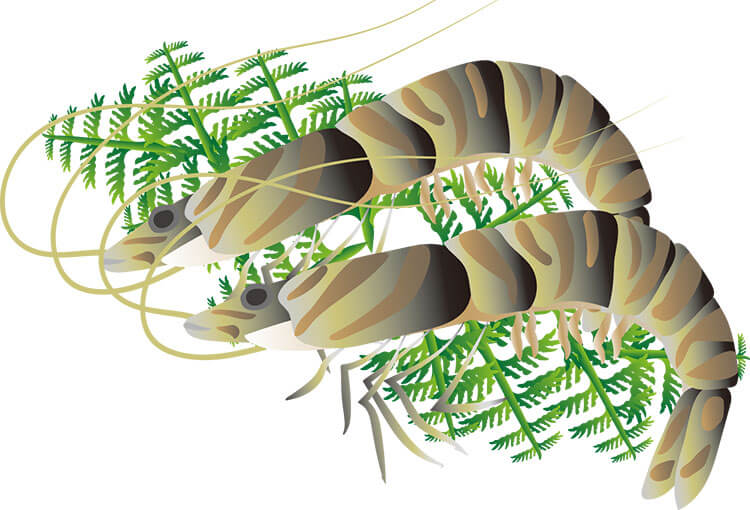
市場やスーパーで買えるエビ・カニ類の中で、養殖できるのはクルマエビだけと言われています。養殖する場所には塩づくりをしていた塩田の跡地などが利用されています。毎年春ごろに卵を採取し、体長15mmくらいまで成長したら池にうつします。クルマエビは寒い時期はエサを食べないため、夏から秋にかけてたっぷりをエサ食べ、冬にかけて出荷というサイクルが一般的です。
マサバ

これまでは主に天然サバの卵を使っていましたが、最近では人工卵を使った完全養殖も出てきました。100~250gの子どもに人工エサをあたえるとおよそ半年後に400g以上に成長し、出荷できるサイズになります。養殖サバは食中毒の原因になるアニサキスがつかないというメリットもあります。
カワハギ
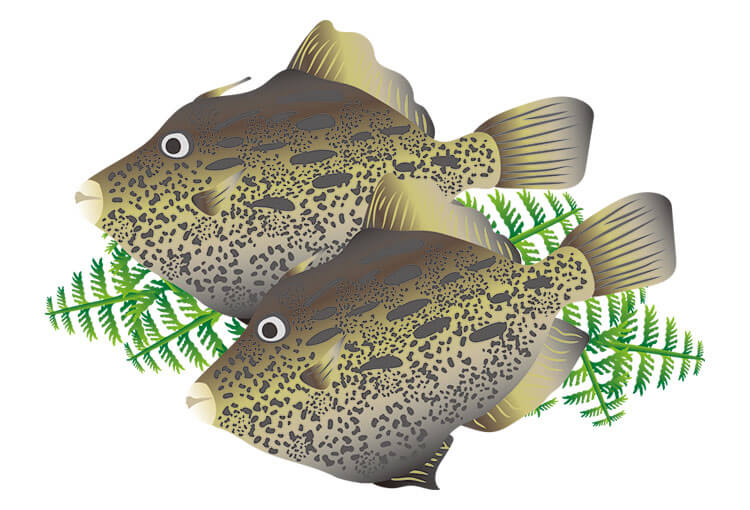
丸くすぼまった口がかわいいカワハギですが、養殖では小さな口でもたっぷり栄養がとれる人工エサを作ることがポイントです。お店に並ぶサイズは体重300~400gほどのもので、成長させるまでに約2年かかります。養殖の白身魚はたくさんありますが、肝まで生で食べられるのはカワハギだけです。