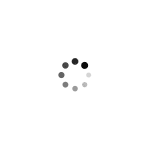江戸時代にタイムスリップしたような世界「商家の町並み」
千葉県立房総のむらの見どころ

江戸時代にタイムスリップしたような世界「商家の町並み」
県内に残る佐原などの古い町並みを参考に、めし屋・そば屋などの飲食店から鍛冶屋までの16軒の店先のほか、旅館の外観を再現した総合案内所の17軒の建物で構成されています。他に古い町並みにはよく見られた、稲荷の社や地蔵、火の見やぐらなども再現しています。
また、商家16軒のうち、8軒の2階は展示室になっており、各店に関係が深い原料・製作工程・道具、技術、製品、販売・流通、年中行事などを紹介しています。
また、商家16軒のうち、8軒の2階は展示室になっており、各店に関係が深い原料・製作工程・道具、技術、製品、販売・流通、年中行事などを紹介しています。
- 総合案内所
 外観は江戸時代後期の旅館を再現しています。モデルとしたのは成田山新勝寺門前にあった大野屋旅館です。昭和2年まで使われていた建物を写真や明治年間の銅板画などを参考にして再現しました。角に「ふさや」と書かれた看板がかけられています。1階は催し物の問い合わせ、見学、製作体験等の受付や案内を行っています。伝統的工芸品、刊行物などを扱う売店もあります。2階は板の間と畳の間の2室があり、研修等に使用しています。
外観は江戸時代後期の旅館を再現しています。モデルとしたのは成田山新勝寺門前にあった大野屋旅館です。昭和2年まで使われていた建物を写真や明治年間の銅板画などを参考にして再現しました。角に「ふさや」と書かれた看板がかけられています。1階は催し物の問い合わせ、見学、製作体験等の受付や案内を行っています。伝統的工芸品、刊行物などを扱う売店もあります。2階は板の間と畳の間の2室があり、研修等に使用しています。 - めし屋(かどや)
 外町場の一膳めし屋を調査し、それをもとに建てられています。店先には「めし處 かどや」と書かれた箱看板を置き、のれんがかかり、店の奥には調理に使うカマドと火床があります。ここでは冠婚葬祭のときに作られてきた太巻き寿司や、季節の素材を用いた房総地方の郷土料理の実演や製作体験を行っています。
外町場の一膳めし屋を調査し、それをもとに建てられています。店先には「めし處 かどや」と書かれた箱看板を置き、のれんがかかり、店の奥には調理に使うカマドと火床があります。ここでは冠婚葬祭のときに作られてきた太巻き寿司や、季節の素材を用いた房総地方の郷土料理の実演や製作体験を行っています。 - そば屋(いんば)
 そばやうどんを食べさせるそば屋を調査し、それをもとに建てられています。「うどん そばきり」とかかれた絵馬状の看板にはそばやうどんをイメージした紙が下がっています。また縄のれんもかかっています。店内の調理場には麺を打つ打ち板、茹でるためのカマドなどがあります。また、客席にはそばのレプリカなどとともに酒徳利も置かれていますが、これは昔「安くて旨い酒を呑むならそば屋」といわれていたことによります。
そばやうどんを食べさせるそば屋を調査し、それをもとに建てられています。「うどん そばきり」とかかれた絵馬状の看板にはそばやうどんをイメージした紙が下がっています。また縄のれんもかかっています。店内の調理場には麺を打つ打ち板、茹でるためのカマドなどがあります。また、客席にはそばのレプリカなどとともに酒徳利も置かれていますが、これは昔「安くて旨い酒を呑むならそば屋」といわれていたことによります。 - 小間物の店(くるり)
 髪飾り・化粧品・袋物などの小間物を売る店を調査し、それをもとに建てられています。店先には「萬小間物るい(よろずこまものるい)」と書かれた板看板があります。店の中には、商品として扱った化粧道具、髪結いの道具、帯締め、羽織紐、袋物などが展示されています。また、帳台や銭箱などが置かれ、帳場の様子を再現しています。ここでは帯締めに使う組紐、小物を入れる袋物、お守りとしてのくくり猿、手まりなどを作る実演や製作体験を行っています。
髪飾り・化粧品・袋物などの小間物を売る店を調査し、それをもとに建てられています。店先には「萬小間物るい(よろずこまものるい)」と書かれた板看板があります。店の中には、商品として扱った化粧道具、髪結いの道具、帯締め、羽織紐、袋物などが展示されています。また、帳台や銭箱などが置かれ、帳場の様子を再現しています。ここでは帯締めに使う組紐、小物を入れる袋物、お守りとしてのくくり猿、手まりなどを作る実演や製作体験を行っています。 - 呉服の店(上総屋)
 衣服の材料の反物を売る店を調査し、それをもとに建てられています。黒漆喰の土蔵造りの建物で、店先には屋号を染め抜いた軒のれんがかかっています。店の中には、反物を入れた桐の呉服箪笥、大八車で品物を運ぶ際に使われた行李・つづらなどが置かれています。また、帳台や帳場格子、銭箱、大福帳などが置かれ、帳場の様子を再現しています。ここでは型染、しぼり染などの染色、作務衣などを作る和裁の実演や製作体験を行っています。2階は展示室になっています。
衣服の材料の反物を売る店を調査し、それをもとに建てられています。黒漆喰の土蔵造りの建物で、店先には屋号を染め抜いた軒のれんがかかっています。店の中には、反物を入れた桐の呉服箪笥、大八車で品物を運ぶ際に使われた行李・つづらなどが置かれています。また、帳台や帳場格子、銭箱、大福帳などが置かれ、帳場の様子を再現しています。ここでは型染、しぼり染などの染色、作務衣などを作る和裁の実演や製作体験を行っています。2階は展示室になっています。 - 辻広場
 江戸時代の町には、人々が集う公共的な広場があり、大きな役割を果たしていました。「むら」の辻広場はそれを再現したものです。江戸の火の見櫓(やぐら)は定火消の発足と共に作られました。高さは約3丈(約9m)で、その後設けられた大名火消屋敷や町の木戸の火見櫓はこれより低くなければなりませんでした。火事を発見すると、定火消は太鼓、大名火消は板木、町方は半鐘を鳴らして知らせました。「むら」の火の見櫓は、7m余の高さがあり、半鐘は、印旛郡白井町富塚(現在の白井市)にある太子堂の半鐘(銘慶応元年)をモデルとして作成しました。
江戸時代の町には、人々が集う公共的な広場があり、大きな役割を果たしていました。「むら」の辻広場はそれを再現したものです。江戸の火の見櫓(やぐら)は定火消の発足と共に作られました。高さは約3丈(約9m)で、その後設けられた大名火消屋敷や町の木戸の火見櫓はこれより低くなければなりませんでした。火事を発見すると、定火消は太鼓、大名火消は板木、町方は半鐘を鳴らして知らせました。「むら」の火の見櫓は、7m余の高さがあり、半鐘は、印旛郡白井町富塚(現在の白井市)にある太子堂の半鐘(銘慶応元年)をモデルとして作成しました。 - 酒・燃料の店(下総屋)
 酒を量り売りした店を調査し、それをもとに建てられています。土蔵造りの建物で、外壁周囲の腰の部分はナマコ壁の装飾がされています。店先には酒屋の看板代わりにかけられていた、杉玉(酒林ともいう)が下げられています。これは新酒ができたことを知らせるものです。店の中には一斗樽、四斗樽や升、徳利を洗うための半切桶などが置いてあります。また、帳台や帳場格子、銭箱などが置かれ、帳場の様子を再現しています。
酒を量り売りした店を調査し、それをもとに建てられています。土蔵造りの建物で、外壁周囲の腰の部分はナマコ壁の装飾がされています。店先には酒屋の看板代わりにかけられていた、杉玉(酒林ともいう)が下げられています。これは新酒ができたことを知らせるものです。店の中には一斗樽、四斗樽や升、徳利を洗うための半切桶などが置いてあります。また、帳台や帳場格子、銭箱などが置かれ、帳場の様子を再現しています。
ここではろうそく作り、果実酒造り、杉玉作りなどの実演や製作体験を行っています。階段は箱階段で、2階は展示室になっています。 - ほかにもたくさんのお店や建物
 薬の店、川魚の店、瀬戸物の店、菓子の店、お茶の店、地蔵、本・瓦版の店、紙の店、細工の店、畳の店、稲荷の社、木工所、鍛冶屋、展示室など。 さまざまなお店を調査して再現いたしました。 それぞれ独自の体験を準備しております。
薬の店、川魚の店、瀬戸物の店、菓子の店、お茶の店、地蔵、本・瓦版の店、紙の店、細工の店、畳の店、稲荷の社、木工所、鍛冶屋、展示室など。 さまざまなお店を調査して再現いたしました。 それぞれ独自の体験を準備しております。