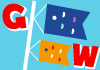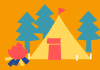文化や習慣が違えば、子育ての常識も変わるもの。そこで、世界の子育て事情を国別にシリーズで紹介していきます。海外ではどんな子育てが行われているのか、実際に現地で暮らすママに実情を明かしてもらいます。
第5回目は、アルゼンチンの首都・ブエノスアイレス在住で、2人の子どもを育てる相川知子さんに現地での子育て事情を聞きました! 赤ちゃんを連れているママが何より優先される社会とのこと。社会的配慮の高さに驚かされますよ。
【世界の子育てシリーズ】各国の子育て事情をチェック!【学校教育】1日の学習時間は基本4時間

ブエノスアイレスの教育システムは、一般的に5歳から義務教育が始まります。その年の6月30日までに満5歳に達する子女から就学し、5歳〜6歳までの義務教育期間は、就学前教育として幼稚園に通います。その後、小学校は6歳から7年間、中高等学校は5年間 となり、合計13年にわたります。
アルゼンチン全体をみても、義務教育期間はほぼ同じで、多くの職場では中高等学校卒が要求されます。ですが、これを修了できるのは、アルゼンチン全体では6割ほど。ブエノスアイレス市内ではこの割合は高くなりますが、地方では小学校を卒業するのがやっとのことが多いです。
公立校と私立校の違い
1クラスあたり20人前後が定員で、特に公立校のプルリンガル校(多言語教育校)が人気です。入学に際しては、すでに通学しているきょうだいがいる家庭と教育関係者の子どもが優先されます。そのほか、学校から1km範囲に住んでいる家庭も優先的に入学できます。最近では、インターネットで登録して、抽選で入学が決まります。一方、私立は一般に面接で多くが先着順です。
公立、私立いずれも、一度入ると同じ系列校の高等部まで進学します。最初の学校選びが大変で、子どもが生まれたら私立の場合は幼稚園の予約が必須になります。公立の場合は、入園半年前にインターネット登録して抽選になります。

我が家の場合は、ブエノスアイレスで26校あるプルリンガル校のうち、三本の指に入る公立小学校に幸いにも入学できました。おかげで、無料で教科書配布や教科書代わりに使うプリントのコピーサービスを受けられ、遠足や特別授業には少額の寄付だけで済んでいます。
ですが、私立に通わせれば、月謝(学費や教材費、お弁当温め代金)だけで、月に800ドル(約8万円)程度はかかるでしょう。私立に通う子は、誕生日会への参加など、学校以外の付き合いでも費用がかかります。家庭環境や収入も関係してくるので、身の丈に合った学校を選ぶことも重要だと思います。
教育は自由と平等が基本

公立校に通う子は、白いエプロンいわば白衣のような「guardapolvo(グアルダポルボ)」が制服です。初めて見たときは、理科の課外授業のようだなと思いましたが、これは「出自にかかわらず、学校では子どもたちは平等であり、白い何も染まらない自由」の象徴を意味しています。100年以上前に、アルゼンチンの教育の父でもある、サルミエント大統領が決めました。現在のアルゼンチンは、自由な意見を尊重し、平等を重視します。
時間は短いが効率的なカリキュラム

国語はスペイン語ですが、プルリンガル校の場合、小学1年生から外国語教育が始まり、英語かフランス語を毎日一時限学びます。英語かフランス語か抽選で指定されたり、のちに外国語科目としてフランス語を選択することもあり、学校によって異なります。プルリンガル校以外の学校でも、一般的に小学4年生から、外国語教育が義務になっています。
ですが、公立校の教育時間はなんと4時間だけです。最初はあまりにも短くてびっくりしました。学校により違いはありますが、小学校は一般的にお昼ご飯を食べた後、午後1時15分から授業が始まり、同じ建物を使う中高等学校は午前中に授業を行います。
なお、私立校は8時間ですが、主要科目4時間のほかに図工や美術、体育の時間があったり、お昼休みが長くなったりするだけで、基本的な学習時間は変わらないそうです。
4時間で十分足りる秘密は「効果的学習」にあります。小学生のときは、科目の境界線が少ないのが特徴です。たとえば、毎年5月25日の革命記念日近くでは、社会で歴史と地理を学習し、国語(スペイン語)も関連する読み物や詩を習い、音楽では国歌と革命記念日の発表会用の寸劇の歌を練習するなど、総合的に学びます。
夏休みは3カ月&宿題もなし
教育面で日本との1番の違いは、12月半ばから翌年3月5日ぐらいまでの期間が夏休みということです。この間、学年が変わるのですが、特に宿題もないため、子どもたちは徹底的に休むことができます。「勉強を忘れるのではないか」と心配するのは私だけで、アルゼンチンの親は誰も心配しません。「子どもたちは毎日学校に通っていて疲れているから、休ませなければいけない」という考えがあるのです。
ブエノスアイレスでは、夏休み期間にお昼ごはん&おやつ付きの無料サマースクールプログラムがあり、親は大助かりです。別途有料になりますが、プールを中心としたサマースクールに1カ月程度入れるのが普通のようです。
長い夏休みですが、市内の芸術や文化講座などに無料参加できる施設やイベントも多数あり、毎日何をしようか困ることも特にありません。親のバケーションは、仕事にもよりますが、通常2週間から1カ月あります。親子一緒に「夏の家(別荘や夏限定で借りる海の近くの家やアパート)」に行って休暇を楽しんだり、旅行に行ったりして過ごします。
【子育て】子どもを見守る文化ながら「生後3日目から寝室は別」

基本的に中学生ぐらいまで、子どもを一人で行動させることはありません。寝ていたり遊んでいるからと、子どもを家において出かけることもあり得ません。
特にブエノスアイレスは、車の交通量が多く、大通りを渡るのは危険です。道自体もでこぼこしていて危ないです。また、誘拐といった治安的な理由もあります。子どもは守られるべき存在であり、1人で歩くのは普通のことではないため、そのような状況を見つけた大人は、どこに保護者がいるのかすぐに探し始めます。
ちなみに、旅行者が子どもをエレベーターに1人で乗せていたり、ショッピングセンターのトイレに1人で行かせているだけでも、「危ない!」と守衛さんがすぐに登場します。旅行の際は注意してくださいね。

私自身、「ぐっすり眠っているから1時間は起きないだろう」と近くのスーパーに15分ほど出かけたことがありましたが、そのときは夫に大変叱られました。我が家の場合、通学や友人宅など、決まった場所への行き来を1人でさせ始めたのが14歳、スーパーなどは16歳ぐらいから立ち寄れるようにしました。
それ以前は、近くても必ず家族が送り迎えをしていて、これが結構大変でした。それでも、忙しい中でも送り迎えの時間は必ず子どもと話ができ、振り返ると「とてもいい時間を過ごせた」と思っています。
とはいえ、親が1日中一緒にいられない場合は、お手伝いさんや祖父母、または友人のお母さんに頼んで預けるなど、何かしらの方法をとらなければいけません。そのため、甥や姪との関わり合いが深い叔父叔母も多いです。祖父母よりも若く、フレキシブルな点でも助かりますね。これは、キリスト教で代理父母になっていることも関係しているのでしょう。
お手伝いさんやベビーシッターも、比較的頼みやすいです。場合によっては、時給5ドル〜7ドル程度(約500円〜700円)でお願いすることもできますし、子育て経験があるお手伝いさんなら、子どもの世話だけではなく、家事もしてくれてとても頼りになります。
赤ちゃんのときから寝室は別
日本よりも子どもと一緒の時間が長いですが、就寝時は赤ちゃんのときから親とは寝室を別にしています。もちろん、何かあればすぐ様子を見ることができるように、家に必ず保護者がいる必要はありますが、出産から2日後に退院して家に戻り、生後3日目から1人で寝ます。
最初のうちは大泣きすることもありますが、きちんとミルクを与え、おむつを取り替え、準備を整えてからドアを閉めます。ひとしきり泣きますが、そのあとはスヤスヤと眠ります。これを繰り返すうちに、就寝時間になると1人でスムーズ寝るようになります。
【医療】有料でも便利な「私立病院ネットワーク」
公立機関であれば、一般に医療費は無料です。時間に余裕があるときや緊急入院の場合は良いのですが、「平等=先着順」という考え方なので、通常は早朝から病院に出向いて整理券を取り、数時間待たなければなりません。こちらの方が病気になりそうです。
そのため、我が家は「私立病院ネットワーク」に入会しています。これは、毎月の掛け金を支払うと、外来診察、緊急診察、入院、手術、レントゲンなどがカバーされるというものです。私が独身時代から入会していたサービスに、子どもたちを入会させました。
追加医療費は、出産費用から子どもたちの内科・外科の外来、歯の矯正に眼鏡の費用まで一切かかっていません。その代わり、毎月200ドル(約2万円)程度支払っています。
【労働環境】バリバリ働く妊婦さんがたくさん
アルゼンチンでは、制度として3カ月間の産休期間があります。内訳は、通常出産前に45日間、出産後に45日間ですが、希望によっては出産ぎりぎりまで働いて、出産後3カ月近く休むことも多いようです。これらはもちろん有給休暇扱いで、授乳のための休憩なども法律で認められています。

いろいろな職業の妊婦さんがいて、その大勢がすぐには産休に入らず、元気に働いていています。そのため、妊婦さんが働くことに誰も不思議がりません。ワールドカップの状況をレポートする妊婦さんもいました。産休後も仕事に復帰することが当たり前です。もちろん、子どもの世話のために、産休後さらに3カ月程度仕事を休む人もいます。
なお、夫の産休制度は特にないですが、出産後2日で退院するので、残業なく早めに帰ることは全く問題ありません。ほかにも、子どもの誕生日などイベント時に仕事を早退したり休んだりしても、仕事には影響ないことが多いです。慣習的に周囲も認めています。
【社会環境】子ども連れへの社会的配慮がすばらしい!
アルゼンチンでは、子どもはとても大事にされます。どんなところでも「子どもの居心地の良さ」が優先されます。社会的弱者の子どもは、保護するのが当たり前という考え方なのだそうです。移民の国であるアルゼンチンは、大変な思いをして新天地にわたってきました。その大地で新しく生まれた命は、大変重要と考えられているからでしょうか。
この考え方のもと、アルゼンチン社会では以下のような社会的配慮があります。
(1)スーパーマーケットに妊婦や赤ちゃん優先レーンを設置
アルゼンチンでは、スーパーの支払い時に、自分の前に2人に並んでいるだけでも、30分以上かかります。優先レーンには一般の人も並べますが、妊婦が来れば「お先にどうぞ!」と譲るのが当たり前です。妊婦も苦しい思いをすることなく、赤ちゃん連れも待つ必要がありません。銀行での手続きや、公共機関でも同様です。守衛さんなどが誘導してくれますし、周りで文句を言う人もいません。
(2)公共交通機関では「高齢者よりも子どもに席を譲る」習慣
高齢者よりも小さな子どもに席を譲る傾向があります。赤ちゃん連れはもちろん、小学低学年以下の子どもがいたら、真っ先に席を譲ってくれます。子どもは身長が低いので、満員電車で大人が周りを囲むと息が苦しいですし、「バスや地下鉄も急ブレーキを踏む可能性があり危ない」という考えです。また、バスの場合はタラップもありますから、ベビーカーを乗せるために手伝ってくれる人も多いです。
もちろん、子連れのお母さんの場合は、お母さんに譲り、子どもは抱っこで座らせたり、また二人席を譲って、子ども三人を座らせたりもします。気づかない若者が座っていたら、子育て経験のある女性などが彼らを諭して、若いお母さんのために、席を譲らせる光景もよく目にします。
(3)遊び場付きのカフェやレストランの存在
ママ友とのお茶会では、プレイルームが併設されていたり、幼稚園教員免許を持つ女性が遊び相手をしてくれるサービスがある飲食店を利用します。子どもメニューの注文が必須など条件付きの場合もありますが、基本無料で利用できます。
フリーランスで働くママも、これなら子ども連れで仕事の打ち合わせができます。ずっと座らせておくのは親子ともにストレスなので、一緒に楽しめることは大変重要です。私もフリーランスで働いていましたので、子ども連れのときはこのようなお店を選んでミーティングを行っていました。
もちろん、このようなサービスがなくても、子ども向けにクレヨンが用意してあるなど、子どもに親切なお店が多く、子どももそうそう騒ぎません。
アルゼンチンには、日本のような電車でのベビーカー移動の不自由さや、子ども連れでのレストランで肩身が狭い思いをするということがありません。キリスト教が国教であり、習慣や文化でもあるため、聖母マリアとそのイエス様のように、お母さんと赤ちゃんがとても神聖視されているからです。赤ちゃんを連れているママが大優先されます。
以上がアルゼンチンの子育て事情です。次回はネパール編をお届けします。
ライター
相川知子(あいかわともこ)
アルゼンチン・ブエノスアイレス在住の通訳者、翻訳者、ライター、日本語スペイン語教師。食品ロジスティックアドバイザー。異文化コミュニケーションアドバイザー。NHKラジオ深夜便ワールドネットワークアルゼンチン担当。16歳と17歳の母。アルゼンチンのことを日本へ発信するのが使命とし、1998年よりインターネットで発信。