子どもはみんな図鑑が大好き。興味の対象はさまざまですが、夢中になって読みふけることもあります。好奇心を育て、考える力を養い、答えを見つける喜びを知る図鑑こそ、子どもの成長に欠かせないものではないでしょうか。とはいえ、無数にある図鑑の中から一冊を選ぶのは大変です。金額もそれなりなので、絵本を買うよりは慎重になります。そこで、図鑑の最新事情と年齢で選ぶおすすめの一冊を専門家に聞きました。
図鑑のトレンドは「ワクワクするようなテーマ」

今回お話を聞いたのは、千葉県立中央博物館で主席研究員を務める斎木健一さん。さまざまな図鑑の監修や発刊に関わり、自身も1000冊以上の図鑑を収集する「図鑑博士」。「マツコの知らない世界」(TBS系)にも出演したほどです。そんな斎木さんにとって、図鑑は「旅行ガイドのようなもの」なのだとか。
「ただの古い建物も旅行ガイドで歴史を知れば違って見えますよね。それと同じで、身近な虫や草花も図鑑で名前を知るだけで興味が湧いてきます。旅行ガイドを読むとワクワクするように、見たことのない生きものやその生息地に思いをはせるのも楽しいものです」
図鑑といえば、ひと昔前は「動物」「植物」「魚」など種類別のものが主流でしたが、最近は「テーマ」がキーワードだといいます。
「たとえば『危険生物』の図鑑がさまざまな出版社から発売されているように、最近は企画性のある図鑑が人気です。その中で、ぜひおすすめしたいのが小学館の『くらべる図鑑』です」
『小学館の図鑑NEO+ くらべる図鑑』

「『くらべる図鑑』は、速さ、大きさ、高さなど、さまざまなテーマで『くらべる』図鑑です。比べる対象も昆虫から宇宙までバリエーション豊か。『くらべる』ことは科学的にものを見る大切な一歩ですから、教育的な意味も大きいですよね」
【新版】小学館の図鑑 NEO+プラス くらべる図鑑(出版社:小学館/本体価格:1,900円+税)
単純な種類別から企画性へ変化した図鑑のトレンド。確かに、思わず手に取ってしまうような楽しい図鑑を書店でもよく見かけますね。
0歳〜小学生高学年まで、年齢別のおすすめ図鑑
どんなに優れた図鑑でも、子どもの年齢に合っていなければ十分に楽しむことができません。そこで斎木さんに、年齢層別におすすめの図鑑を教えていただきました。
0歳〜3歳向け
『BCキッズ おなまえ いえるかな? はじめてのずかん300 英語つき』

■特長&おすすめポイント
「カブトムシから消防車まで、子どもの好きなものを広範囲で網羅した図鑑。まだ興味の対象が固まっていない小さな子どもに見せてあげて、お気に入りを見つけましょう。すでに好きなジャンルのある子に見せて、ほかの世界を開拓させてもいいですね」
(出版社:講談社/本体価格:980円+税)
3歳〜5歳向け(幼稚園児)
『はっけんずかん』シリーズ

■特長&おすすめポイント
「イラストのあちこちに小さなしかけ扉があり、そこをめくると、なぞの答えや生きものの見えなかった部分がみえます。子どもと一緒に読めば、『どうなっちゃうんだろう?』とワクワクしながらページをめくる楽しさがあります」
(出版社:学研/本体価格:1,880円+税)
※図鑑の種類によって価格が異なります
『せんせい!これなあに?』シリーズ

■特長&おすすめポイント
「写真がとてもリアルなシリーズ。『野はらの葉っぱ』『木の実・草の実』などは、野原から取ってきて、そのまま紙の上に置いたかのようです。写真が大きく文字も少ないので、絵本の読み聞かせと同じように親子で楽しめます」
(出版社:偕成社/本体価格:1,600円+税)
6歳〜9歳向け(小学校低学年)
『生きもの つかまえたら どうする?』

■特長&おすすめポイント
「とにかく子どもは生きものを捕まえます。でも、その後はどうすればいいのでしょうか? どう持ち帰れば死なないのか、どう飼うのか、いつまで飼えるのか、飼いきれなくなったらどうすればよいのかなど、捕まえ方とその後のことを丁寧に解説した図鑑です」
(出版社:偕成社/本体価格:1,500円+税)
10歳〜12歳向け(小学校高学年)
『チリメンモンスターをさがせ!』

■特長&おすすめポイント
「ちりめんじゃこやシラスをよく見ると、ほかの種類の魚や小さなカニ、エビ、イカ、タコなどが混じっていることがあります。そんな『チリメンモンスター』を親子で探しながら、海の生態系に思いをはせることができる図鑑です」
(出版社:偕成社/本体価格:1,600円+税)
『鳥のフィールドサイン観察ガイド』

■特長&おすすめポイント
「地面に落ちた羽、足跡、糞など、鳥が残した『フィールドサイン』を楽しむ図鑑です。それらを探すコツや採集・保存方法が紹介されていて、自由研究にもぴったりです」
(出版社:文一総合出版/本体価格:2,000円+税)
【番外編】生き物以外の図鑑
生き物の図鑑を中心に紹介いただきましたが、ほかにもさまざまな図鑑が出ています。そんな「生き物以外の図鑑」についてもおすすめを聞きました。
『街角図鑑』
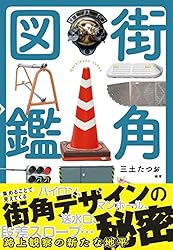
■特長&おすすめポイント
「マンホールや電柱から、『単管バリケード』『のぼりベース』のような名前は知らないけれどどこにでもあるものまで、街角にあるものについて詳しく解説している図鑑です。わが家の子どもたちの間でブームになりました」
(出版社:実業之日本社/本体価格:1500円+税)
『すし図鑑』

■特長&おすすめポイント
「寿司だけでなく、さばかれる前の魚の姿も載っています。ネタの味わいや歴史など、うんちくも盛りだくさん。大人向けの図鑑ですので、お父さんやお母さんが子どもに説明してあげてください」
(出版社:マイナビ出版/本体価格:1,400円+税)
知れば知るほど奥深い図鑑の世界。まずはここで紹介した図鑑を子どもにプレゼントしてみて、親子で楽しみながら次の一冊を探してみてはいかがでしょうか。
重たい図鑑と上手に付き合う方法は?

図鑑の多くは分厚く、重たく、サイズもかさばるもの。いつでも持ち歩くわけにはいきませんよね。そんな図鑑と上手に付き合う秘訣は、「スマートフォンやデジカメの活用」にあるそうです。
「きれいな花、めずらしい虫などと出会ったら、スマートフォンのカメラやデジカメで撮影して、家に帰ってから図鑑で調べましょう。写真に撮影場所と撮影日、図鑑で調べた名前を添えると、自然と自分だけの図鑑ができあがります」
「撮影のコツは何枚も写真をとることです。たとえばチョウなら、近づきながら何枚も撮る。花だったら、全体、花の拡大、葉の拡大と場所を変えて撮るようにすれば、図鑑を見たときに調べやすくなります」
子どもにスマートフォンを持たせるのがまだ早ければ、コンパクトなデジカメを持たせてもいいかもしれません。撮ったものを親子で見れば盛り上がりそうです。
図鑑アプリもおすすめ!
最近は、VR技術などを使ってスマートフォンと連動させた図鑑もあります。そういった「ハイテク図鑑」はいかがでしょうか?
「VRを使って恐竜が動く図鑑などもありますが、ページを開いて、スマートフォンのアプリを起動して、画面を認識して…とかなり面倒。ハイテクを求めるなら、無理に紙とデジタルを融合させたものより、ストレートに図鑑アプリをオススメします」
図鑑アプリならかさばらないうえに、検索も簡単。鳴き声を入れるなどの機能も搭載できます。そんな図鑑アプリのおすすめを2つ紹介してもらいました。
星座表

「スマートフォンをかざすとその方向の星空が画面に表示され、親子で星空を眺めて星座の勉強ができます。このアプリに勝る星座図鑑を知りません」
星座表をダウンロードする【iPhone用】星座表をダウンロードする【Android用】野鳥の鳴き声図鑑

「羽根の色や体の大きさ、棲んでいる場所などで鳥の名前を検索でき、鳴き声も聞ける図鑑アプリ。ヒヨドリ、ムクドリ、シジュウカラなど、声は聞き覚えがあるけど姿は知らない鳥について調べるのも楽しいですよ」
野鳥の鳴き声図鑑をダウンロードする【iPhone用】一方、紙の図鑑は見やすく、感覚でページをめくる楽しさがあります。アプリと紙、目的に合わせて選ぶのがかしこい図鑑の楽しみ方といえそうです。
子どもの「なぜ?」「どうして?」という疑問に応え、知的好奇心を満たしてくれる図鑑。大人にとっても「知らないことを知る」経験はワクワクするものです。さっそく、子どもと一緒に書店の図鑑コーナーへ足を運んでみてはいかがでしょうか?








