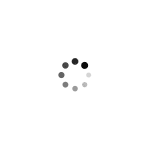「災害時のメディアリテラシーを考えよう」
ニュースパーク(日本新聞博物館)のお知らせ
災害時のメディアリテラシーを考えよう
2023年08月21日 15時16分
※営業時間や定休日などは最新の情報ではない可能性があります。
お出かけ前に最新の公式情報を、必ずご確認下さい。
お出かけ前に最新の公式情報を、必ずご確認下さい。
企画展「そのとき新聞は、記者は、情報は――関東大震災100年」開催

ニュースパークは8月26日(土)から12月24日(日)まで、企画展「そのとき新聞は、記者は、情報は――関東大震災100年」を開催します。
今年9月1日で関東大震災発生から100年を迎えるのを機に、新聞社の当時の状況、記者が被災地で見たもの・経験したこと、横浜・神奈川がどのように伝えられたのかを、当時の紙面や写真で振り返ります。
そこには、どんな状況でも人々に情報を届けようとする新聞社と記者の「本能」とも言える姿があります。災害時に広がる流言・デマも紹介し、不確かな情報にどう対処するかを考える機会にもします。関東大震災前後の震災、新聞社の防災・減災の取り組みも取り上げます。
今後必ず起こる大震災に向けて、ご家族で災害時の情報との付き合い方について話し合ってみませんか?
〈展示構成〉
Ⅰ「震災発生 そのとき新聞社は、新聞は、記者は」
1923年9月1日午前11時58分、相模湾北西部を震源とするマグニチュード7.9の巨大地震が発生、関東地方を中心に激震が襲いました。東京の新聞社も被災し、社屋の焼失を免れたのは4社だけでした。新聞発行が困難に陥る中、各社は足踏み式の印刷機などを使って号外を発行しました。また、大阪にも拠点を持つ東京の新聞社は大阪に記者を派遣、各地の新聞社も被災地に特派員を送り出しました。途中、鉄橋が落ちた相模川を泳いで渡るなど、数々の苦難を経て、目的にたどりつきました。当時の新聞社の状況、記者たちが目にしたもの・経験したことを、当館所蔵の当時の紙面などで振り返ります。
Ⅱ「震源地・神奈川、横浜はどのように伝えられたか」
中央防災会議(事務局・内閣府)の「災害教訓の継承に関する専門調査会」が2006年にまとめた報告書によると、神奈川県は死者数(行方不明者を含む)が3万2838人、住家被害棟数が12万5577棟で、住家の全半壊は東京を上回りました。生糸の輸出港の横浜港も壊滅的な被害を受けました。根府川駅付近(小田原市)で発生した地滑りと土石流災害、鎌倉の沿岸部を襲った津波などによる被害も大きなものでした。当時、横浜は「横浜貿易新報」「横浜毎朝新報」「横浜日日新聞」が本社を置いていましたが、いずれも被災して新聞発行が困難になりました。大震災直後、各地の新聞が横浜、神奈川の被害状況を連日伝えましたが、その中には不確かな情報も含まれていました。そうした中、流言や不安を排し、正確な情報を伝えるために、横浜市は地元3紙の協力で「横浜市日報」を9月11日付から発行。同13日からは横浜貿易新報が臨時号を発行しました。震災直後から、横浜、神奈川がどのように伝えられたのかを、紙面と新聞社提供写真で紹介します。
Ⅲ「不確かな情報、流言・デマ、混乱」
震災直後、電信・電話が途絶え、各官庁の連絡もままならなくなりました。当時多くの人々が新聞報道を情報を得る上で頼りにしていましたが、新聞社も新聞発行が困難になりました。そうした中、地震の発生原因、津波、政治家の生存などに関する確かではない情報が入り乱れました。特に、被災地から離れた地域では、被災地の状況や飛び交う情報の真偽を確かめるすべがなく、不確かな情報が新聞に掲載されることがありました。なかでも、朝鮮人が震災に乗じて「放火した」「井戸に毒を入れた」などの流言・デマは、それらを信じた人たちに多数の朝鮮人が虐殺された事件を生みました。このような確かでない情報が載った当時の紙面を紹介するとともに、阪神・淡路大震災、東日本大震災、熊本地震などでデマが広がっていることに対し注意を呼び掛けた記事も取り上げ、災害時の不確かな情報にどう対処するかを考えます。
Ⅳ「関東大震災前後の震災、新聞社の防災・減災の取り組み」
安政江戸地震、明治三陸地震津波をはじめ関東大震災以前の震災を報じた錦絵、新聞本紙や新聞附録、北丹後地震、東南海地震などの関東大震災以降の震災を報じた号外や紙面を展示します。併せて、これから発生の可能性が指摘されている地震についての各社の報道や、各紙の防災・減災の取り組みも紹介します。

ニュースパークは8月26日(土)から12月24日(日)まで、企画展「そのとき新聞は、記者は、情報は――関東大震災100年」を開催します。
今年9月1日で関東大震災発生から100年を迎えるのを機に、新聞社の当時の状況、記者が被災地で見たもの・経験したこと、横浜・神奈川がどのように伝えられたのかを、当時の紙面や写真で振り返ります。
そこには、どんな状況でも人々に情報を届けようとする新聞社と記者の「本能」とも言える姿があります。災害時に広がる流言・デマも紹介し、不確かな情報にどう対処するかを考える機会にもします。関東大震災前後の震災、新聞社の防災・減災の取り組みも取り上げます。
今後必ず起こる大震災に向けて、ご家族で災害時の情報との付き合い方について話し合ってみませんか?
〈展示構成〉
Ⅰ「震災発生 そのとき新聞社は、新聞は、記者は」
1923年9月1日午前11時58分、相模湾北西部を震源とするマグニチュード7.9の巨大地震が発生、関東地方を中心に激震が襲いました。東京の新聞社も被災し、社屋の焼失を免れたのは4社だけでした。新聞発行が困難に陥る中、各社は足踏み式の印刷機などを使って号外を発行しました。また、大阪にも拠点を持つ東京の新聞社は大阪に記者を派遣、各地の新聞社も被災地に特派員を送り出しました。途中、鉄橋が落ちた相模川を泳いで渡るなど、数々の苦難を経て、目的にたどりつきました。当時の新聞社の状況、記者たちが目にしたもの・経験したことを、当館所蔵の当時の紙面などで振り返ります。
Ⅱ「震源地・神奈川、横浜はどのように伝えられたか」
中央防災会議(事務局・内閣府)の「災害教訓の継承に関する専門調査会」が2006年にまとめた報告書によると、神奈川県は死者数(行方不明者を含む)が3万2838人、住家被害棟数が12万5577棟で、住家の全半壊は東京を上回りました。生糸の輸出港の横浜港も壊滅的な被害を受けました。根府川駅付近(小田原市)で発生した地滑りと土石流災害、鎌倉の沿岸部を襲った津波などによる被害も大きなものでした。当時、横浜は「横浜貿易新報」「横浜毎朝新報」「横浜日日新聞」が本社を置いていましたが、いずれも被災して新聞発行が困難になりました。大震災直後、各地の新聞が横浜、神奈川の被害状況を連日伝えましたが、その中には不確かな情報も含まれていました。そうした中、流言や不安を排し、正確な情報を伝えるために、横浜市は地元3紙の協力で「横浜市日報」を9月11日付から発行。同13日からは横浜貿易新報が臨時号を発行しました。震災直後から、横浜、神奈川がどのように伝えられたのかを、紙面と新聞社提供写真で紹介します。
Ⅲ「不確かな情報、流言・デマ、混乱」
震災直後、電信・電話が途絶え、各官庁の連絡もままならなくなりました。当時多くの人々が新聞報道を情報を得る上で頼りにしていましたが、新聞社も新聞発行が困難になりました。そうした中、地震の発生原因、津波、政治家の生存などに関する確かではない情報が入り乱れました。特に、被災地から離れた地域では、被災地の状況や飛び交う情報の真偽を確かめるすべがなく、不確かな情報が新聞に掲載されることがありました。なかでも、朝鮮人が震災に乗じて「放火した」「井戸に毒を入れた」などの流言・デマは、それらを信じた人たちに多数の朝鮮人が虐殺された事件を生みました。このような確かでない情報が載った当時の紙面を紹介するとともに、阪神・淡路大震災、東日本大震災、熊本地震などでデマが広がっていることに対し注意を呼び掛けた記事も取り上げ、災害時の不確かな情報にどう対処するかを考えます。
Ⅳ「関東大震災前後の震災、新聞社の防災・減災の取り組み」
安政江戸地震、明治三陸地震津波をはじめ関東大震災以前の震災を報じた錦絵、新聞本紙や新聞附録、北丹後地震、東南海地震などの関東大震災以降の震災を報じた号外や紙面を展示します。併せて、これから発生の可能性が指摘されている地震についての各社の報道や、各紙の防災・減災の取り組みも紹介します。
ニュースパーク(日本新聞博物館)のお知らせ一覧

「ニュースを伝える情報デザイン」展開催
ニュースパーク(日本新聞博物館)は9月7日(土)から12月22日(日)まで、企画展「ニュースを伝える情報デザイン インフォグラフィックスと新聞整2024年08月15日 10時56分
「新型コロナと情報とわたしたちⅡ」開催
ニュースパーク(日本新聞博物館)は、2024年4月20日(土)から9月1日(日)まで、企画展「新型コロナと情報とわたしたちⅡ―コロナがわたしたちに2024年04月05日 10時28分
災害時のメディアリテラシーを考えよう
企画展「そのとき新聞は、記者は、情報は――関東大震災100年」開催ニュースパークは8月26日(土)から12月24日(日)まで、企画展「そのとき新聞2023年08月21日 15時16分
企画展「海からのメッセージ」開催!
ニュースパーク(日本新聞博物館)は、9月10日(土)から12月25日(日)まで、企画展「海からのメッセージ――海洋環境と報道」を開催します。2022年09月09日 16時38分
「近代日本のメディアにみる怪異」開催
企画展「近代日本のメディアにみる怪異」は、妖怪、幽霊、超常現象などの「怪異」について、明治時代以降の新聞がどのように伝えてきたのか、所蔵資料を中心2022年04月13日 15時26分
企画展「沖縄復帰50年と1972」を開催
夏休みに沖縄旅行を計画しているご家族におすすめ!現地を観光する前に、歴史に触れてみませんか? ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~2022年04月13日 15時19分
「2021年報道写真展」を開催します
ニュースパーク(日本新聞博物館)は、2022年1月8日(土)から4月17日(日)まで、企画展「2021年報道写真展」(東京写真記者協会と共催)を開2021年12月22日 14時57分
宇宙飛行士野口聡一さんの活躍も紹介します
ニュースパーク(日本新聞博物館)と神奈川新聞社は、2021年10月2日(土)から12月26日(日)まで、企画展「ペンを止めるな! 神奈川新聞1302021年09月29日 14時59分ミニ展示 企画展で振り返る20年のあゆみ
ニュースパーク(日本新聞博物館)は10月12日、開館20周年を迎えました。当館20年のあゆみを過去の企画展で振り返ります。本来は20周年記念企画展2021年04月14日 11時35分
企画展「東京五輪・パラリンピック報道展」
ニュースパーク(日本新聞博物館)は、4月24日(土)から9月26日(日)まで、「東京五輪・パラリンピック報道展 幻の一九四〇東京五輪からTOKYO2021年04月13日 13時38分
企画展「東日本大震災展」
ニュースパーク(日本新聞博物館)は、4月24日(土)から9月26日(日)まで、企画展「伝える、寄り添う、守る――『3・11』から10年」(特別協力2021年04月13日 13時35分
企画展「石川文洋展」
2020年10月3日(土)から12月20日(日)まで、企画展「80歳の列島あるき旅・石川文洋写真展 フクシマ、沖縄…3500キロ」(共同通信社と共2020年09月28日 16時01分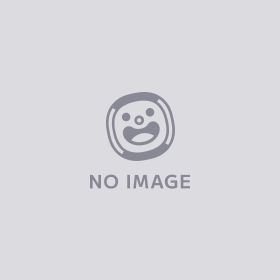
終了・企画展「2019年報道写真展」
新元号「令和」への改元、皇位継承に伴う新天皇陛下の即位と、新たな時代の幕開けとなった2019年。今なお記憶に新しいラグビーワールドカップ(W杯)日2020年09月28日 15時48分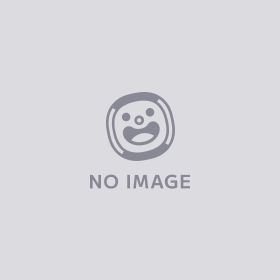
臨時休館のお知らせ
当館は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、3月22日まで臨時休館としていましたが、現下の状況を踏まえ、当面の間、休館します。再開の予定が決まり2020年03月23日 17時03分
企画展「地域の編集」
このデジタル時代に、各地で洗練された紙メディア(ローカルメディア)をつくり、人と地域のつながりを生み出している人たちが増えています。新聞社の活動に2019年10月21日 13時35分