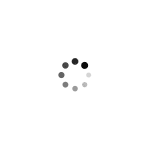香取市立神南小学校「火起こし」体験記
千葉県立房総のむらの見どころ

香取市立神南小学校「火起こし」体験記
「風土記の丘」に、香取市立神南小学校6年生の皆さんが勉強に来ました。最初に「資料館」の展示品について勉強して、その後に「火起こし」体験です。昔から行われてきた「火起こし」では、「打撃法」と「摩擦法」がよく知られています。まずは、「火打ち石」に「火打ち鉄(かね)」を打ちつけて「火花」をだす、「打撃法」での体験をしていただきました。テレビドラマなどでも、この「火花(切り火)」で送り出すシーンを見たことがあると思います。
- 火起こしをするこどもたち
 「木」と「木」の”摩擦熱”で「火起こし」をする場合に多いのは、「キリ」状の棒を「木(板)」の上で回転させて摩擦で熱エネルギーを作りだす方法で、「キリモミ」「紐キリ」「弓キリ」「マイギリ」式などがあります。今回は「マイギリ」を使って”火を起こし”ます。「マイギリ」では、中心の「火きり杵(きね)」を「火きり臼(臼)(刻みが入れられている)」の上で回転させて、”焦げた高温の木くず”を作り出します。この”木くず”が「火種(ひだね)」となります。
「木」と「木」の”摩擦熱”で「火起こし」をする場合に多いのは、「キリ」状の棒を「木(板)」の上で回転させて摩擦で熱エネルギーを作りだす方法で、「キリモミ」「紐キリ」「弓キリ」「マイギリ」式などがあります。今回は「マイギリ」を使って”火を起こし”ます。「マイギリ」では、中心の「火きり杵(きね)」を「火きり臼(臼)(刻みが入れられている)」の上で回転させて、”焦げた高温の木くず”を作り出します。この”木くず”が「火種(ひだね)」となります。  できた「火種」を「火口(ほくち)」に移します。「火口」は、”ヨモギ”や”綿”などでもいいですね。今回は”麻紐”の撚りを戻して、繊維状にした”麻わた”を使用しました。
できた「火種」を「火口(ほくち)」に移します。「火口」は、”ヨモギ”や”綿”などでもいいですね。今回は”麻紐”の撚りを戻して、繊維状にした”麻わた”を使用しました。
「火口」に包まれた「火種」に向かって息を吹きかけて、火力を高めます。あまり強く吹きかけなくても、口先を尖らせて「火種」を狙って吹きかければ十分です。
息を吹きかけ続けると、火が「火種」から「火口」に移り、さらに火力が高まると、白い煙が少しづつ濃くなってきたかと思うと、”一気にボッ”と”炎”になります。「火口」を扱い安くするために、「土器」(新しく焼いた)を使用しています。昔もこんなふうにしていたのでしょうね。 体験者全員が「マイギリ」での「火起こし」に成功です。「マイギリ」とともに記念撮影です。なぜか、一人”変なおじさん(館職員)”も写っていますが、、、先端に「火きり杵」が付けられた”丸棒”には紐が結ばれ、その紐は丸棒が通された板(「はずみ板」)につながっており、この「はずみ板」を上下することで、「火きり杵」に高回転を与えることができる仕組みです。また、この「マイギリ」には、回転を補助してくれる、”おもり”となる「はずみ車」もついていて、「はずみ板」の”上げ下げ”のタイミングとコツをつかめば意外と簡単に「火種」を作ることができます。
体験者全員が「マイギリ」での「火起こし」に成功です。「マイギリ」とともに記念撮影です。なぜか、一人”変なおじさん(館職員)”も写っていますが、、、先端に「火きり杵」が付けられた”丸棒”には紐が結ばれ、その紐は丸棒が通された板(「はずみ板」)につながっており、この「はずみ板」を上下することで、「火きり杵」に高回転を与えることができる仕組みです。また、この「マイギリ」には、回転を補助してくれる、”おもり”となる「はずみ車」もついていて、「はずみ板」の”上げ下げ”のタイミングとコツをつかめば意外と簡単に「火種」を作ることができます。 続いては、先端に「火きり杵」がついた”丸棒”だけで「モミキリ」体験です。こちらは、「火きり杵」を早く回転させるための補助はありませんので、ただ”人力”だけで摩擦による熱エネルギーを作らなければなりません。”大変です” ”疲れます”「はずみ車」の付いた「マイギリ」が、いかにすごい「道具」だかわかると思います。
続いては、先端に「火きり杵」がついた”丸棒”だけで「モミキリ」体験です。こちらは、「火きり杵」を早く回転させるための補助はありませんので、ただ”人力”だけで摩擦による熱エネルギーを作らなければなりません。”大変です” ”疲れます”「はずみ車」の付いた「マイギリ」が、いかにすごい「道具」だかわかると思います。 これは大変そうだということで、校長先生も参加です。「火きり杵」のついた”丸棒”を掌で回転させて、「火きり臼」との摩擦温度を上げていきますが、温度が下がると「火種」となる高温の”木くず”は出てきませんので、温度を下げないために回転を止めないようにして一人が終わったら次の人にバトンタッチです。この状態を少し続けると、「マイギリ」と同じように、温度が上がり「火種」ができてきます。神南小学校の皆さんんはチームワークもよく、この方法でも「火起こし」ができました。しかし「疲れた」「筋肉痛だ」とは、実感でしょう。
これは大変そうだということで、校長先生も参加です。「火きり杵」のついた”丸棒”を掌で回転させて、「火きり臼」との摩擦温度を上げていきますが、温度が下がると「火種」となる高温の”木くず”は出てきませんので、温度を下げないために回転を止めないようにして一人が終わったら次の人にバトンタッチです。この状態を少し続けると、「マイギリ」と同じように、温度が上がり「火種」ができてきます。神南小学校の皆さんんはチームワークもよく、この方法でも「火起こし」ができました。しかし「疲れた」「筋肉痛だ」とは、実感でしょう。