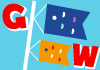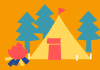子どもが2歳〜3歳くらいになると、自分がやりたいことを主張するようになります。自己主張はとても大切なことですが、それと同時に親が悩むのがワガママへの対処法や我慢のさせ方ではないでしょうか。
そこで今回は、心理学をベースにカウンセリングやセミナーを行う「未来クリエイション」でトレーナーとして活躍しながら、数々の育児本を出版している田嶋英子さんに、子どもが社会生活を送る上で必要な自己抑制力の育て方について教えてもらいました。
自己抑制力とは?

自己主張ができるようになるのは、子どもが成長した証。ですが、いつでも自分の思い通りに行動できるわけではありません。そういった時に必要になるのが「自己抑制力」です。
「自己抑制力とは、自分がやりたいことと集団の中で望まれることが一致していないときに、自分の気持ちや行動をコントロールする力です。小さな子どもはできないのが当たり前ですから、なんとかできるように導いてあげる必要がありますね」
今まで家庭の中で好きなように過ごしてきた子どもが、幼稚園や保育園など集団の中に入ることで「自分の主張が通らないことがある」ということを経験します。そのときに必要になってくるのが、感情をコントロールする力、自己抑制力というわけです。
どこからが「ワガママ」? どう判断する?

では、一体どこからが「ワガママ」になるのでしょうか。
「何が『ワガママ』なのかは、それぞれ家庭の判断でよいのではないでしょうか。集団の中でどのように過ごしてほしいのか、お母さんやお父さんの考えを根気強く伝えていきましょう」
なんでもかんでもワガママだと決めつけるのではなく、時と場合によって許されることと許されないことがあるということを伝えていけばいいとのこと。
「一番いけないのは、できなくて当たり前だからと放っておいたり、叱りつけたりすることです。放っておけば何がいけないことかわからないままですし、叱って押さえつけてしまうと自分から表現することができなくなってしまいます」
また、ワガママは言わないより言った方が子どもの成長に繋がるそう。
「ワガママが言えるということは、自分の意見を言えるということ。それによって、周りの人との衝突が起こり、子どもはそこで初めて自分以外の人にも言いたいことがあることを知ります」
「さらに、ワガママを言い合うことで、相手との折り合いをつける力を身につけていきます。最初は親が折衷案を提案するなどして手助けし、最終的には自分で判断できるようにしてあげましょう」
逆に、ワガママを押さえつけてしまうと、子どもは自分の意見を言わなくなるそう。子どもの意見をしっかりと受けとめ、個性をつぶさないように育ててあげたいですね。
自己抑制力を育てるトレーニング
では、具体的にどのようにすれば自己抑制力を育てられるのか、効果的なトレーニング方法を聞きました。
(1)カードを使ったトレーニング(2歳〜3歳から)
「視覚に訴えて、動作をコントロールするトレーニングです。さまざまなシチュエーションが描かれたカードを用意して、子どもに真似をさせます。市販のカードや手作りのカードを使いましょう」
例えば…・公共の場で大きな声で話している→口元に指をあてて「しーっ」のポーズをとっている絵が描かれたカードを見せる→子どもは見た絵を真似て静かにする
・走ってはいけないところで走り回る→走っている絵に×がついているカードを見せる→走るのをやめる
「体を動かしているときや、何かに夢中になっているときなど、口で伝えても理解できない場合に有効です。また、カードを使うことで親が大きな声を出して注意する必要もなくなります」
こうしてほしいと思う場面に合わせたカードを作っておくといいですね。
(2)手をつないで歩く(3歳〜4歳から)
「親子で手をつないで歩くだけでも、社会性を培うトレーニングをすることができます。歩幅をそろえたり、呼吸をそろえたりと、相手を意識することで社会性が身につきます」
「お母さんやお父さんが手をつないで歩く場合に大切なのは、子どもと意識を一緒にすること。片手でスマホをいじったり、別の人とのおしゃべりに夢中になったりしていると、トレーニングにはならないので注意しましょう」
(3)ストップウォッチを使う(4歳〜5歳から)
「ストップウォッチを使って、『待てる力』を育てるトレーニングです。目の前に遊びたくなるおもちゃや本などを置き、触っていいと言うまで触らないように伝えます。その後ストップウォッチを使って時間を計ります。決めた時間まで触らずに待てたらOKです」
きょうだいや友達とゲームのようにやってみてもいいですね。
日常生活にも自己抑制力を育むヒントがたくさん!

また、日常生活の中でも自己抑制力を育むトレーニングに繋がる場面はたくさんあるそうです。
「例えば、『いただきます』のあいさつです。家族で食卓を囲んで『いただきます』をしてから揃って食事を始めるのは、実は『時間やタイミングを合わせる』トレーニングになっています」
これ以外にも、子どもの自己抑制力を伸ばすヒントがたくさんありそうですね。日常生活の中で、少し意識してトレーニングを取り入れながら、子どもの我慢する気持ちや人を思いやる気持ちを育ててあげたいですね。
さらに、親自身が気をつけることもあるようです。
「子どもは親がしていることを見て真似します。親の真似をするということは、親がやらないことはやらないということです。『約束を守らない』『言われたことをしない』など、子どもに注意する前に一度、自分の普段の生活を振り返ってみましょう」
最後に、子どもが集団生活を始めるまでは「あなたが一番大切」ということを繰り返し伝えてあげてほしいと田嶋さん。
「自分が一番大切だと感じている子どもは、人のことも大切にできます。そうすると自ら我慢できるようになります。無理に『させられる』我慢ではなく、自分から我慢できることは、自己抑制力が身についていることになります」
自己抑制力を育てるには、親も楽しみながらやるのがいいとのこと。とくに小さな子どもほど、根気強く丁寧に説明を繰り返すことが必要なので、手軽にできるトレーニングを日常生活に取り入れるなどして、焦らずゆっくりと取り組んでくださいね。