トイレトレーニングが終了しておむつがとれても、夜のおねしょを卒業するまでには時間がかかります。濡れた布団を見てガミガミ叱ってしまう朝…親にとっても子どもにとってもストレスですよね。我が子がおねしょを卒業するまでに親は何をしたらいいのか、その対処法について、トイレトレーニングアドバイザー(R)の珠里さんに教えていただきました。
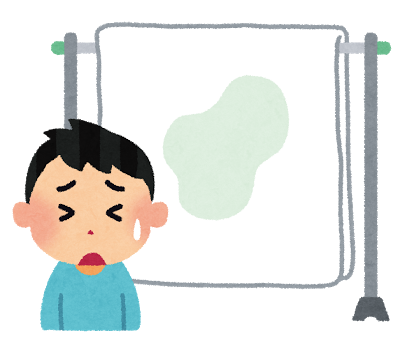 日中のトイレは完璧なのに、夜のおねしょはなくならない。「うちの子はどうして?」と困っているお父さんお母さんは多いと思います。でも、眠っている間のおねしょは、その子自身が原因でないことのほうが多いと珠里さんは言います。
日中のトイレは完璧なのに、夜のおねしょはなくならない。「うちの子はどうして?」と困っているお父さんお母さんは多いと思います。でも、眠っている間のおねしょは、その子自身が原因でないことのほうが多いと珠里さんは言います。
「おねしょの原因は、まず、膀胱の機能が未発達だからということが第一です。それから、夜、眠っているときは無意識であるということ。日中は『おしっこしたい』という感覚を感じ取れるようになっていても、睡眠中は無意識ですから。膀胱におしっこが溜まったら自然に出てしまう習慣が残っていますよね。」
日中はおむつがとれていても、夜間のおねしょが心配でしばらくの間、夜は紙おむつを利用しているおうちが多いですよね。そこで、夜のおむつがとれるタイミングを教えてもらいました。
「眠ってから2~3時間後におしっこをしているお子さんは、まだ膀胱が成長しきれていなくて、おしっこを溜められない状態です。そういう子に『夜も紙おむつをはずしましょう』としてしまうと、ストレスになってしまいますので、引き続き紙おむつを利用していいと思います。明け方の4時5時くらいまでおしっこをしていないなら、もう膀胱が成長しているという目安なので、布パンツに替えてもいいと思います。」
膀胱の成長は目で見えないだけに判断が難しいもの。おむつのおしっこチェックラインを見ることで、タイミングを探ってみましょう。
「眠っているときに無理やり起こすというのは、睡眠の妨げになるし、お昼に眠くなってしまうし、体調不良の原因にもなりますよね。『どうしても』というのであれば眠りの浅そうなときを見計らって声をかけて、トイレに連れて行くといいと思います。」
明け方におもらしをしてしまうお子さんに対しては、その時間に起こしてトイレに連れて行くのはありだそう。
また、ある程度の年齢になったら親は覚悟を決めて布パンツをはかせるのも手なのだとか。
「5歳、6歳、小学生になっても紙おむつをはいて眠るというのは、股関節を締めつけられるし、あまりいい傾向ではないですね。おねしょが毎日じゃなくて週1度あるかないかだったら、お父さんお母さんが覚悟して布パンツにしてあげるのがいいと思います。そのことによってお子さん自身も意識ができるので、意外とスムーズに布パンツへ移行できることもあるんです。」
おねしょを恐れるあまり、ずるずると紙おむつに頼ってしまいがちですが、おむつはずれには思い切りも必要なんですね。
「まずは、おねしょ専用のお布団で寝かせることですね。防水シーツを敷いて、そこで寝てもらいましょう。それでもパジャマやお布団が濡れてしまうのがどうしてもイヤだというのであれば、布パンツの上に紙おむつをはかせて寝かせる方法もあるし、お子さんが寝入ったら紙おむつをはかせる方法もあります。」
また、親子で相談しながらおねしょ対策を決めるということも大切なのだそう。
「少し大きくなると、紙おむつを絶対にはきたくないというお子さんもいるので、そこはお子さんと話し合って決めるのがいいと思います。うちは、捨てる覚悟で安いお布団を買って、乾かない時期は布団乾燥機を使っていましたね。」
最初からおねしょをしていい状況を作っておけば、親のストレスもぐっと減りそうですね。
 それでも我が子のおねしょが続くと、ついついイライラして、いろいろ言いたくなってしまいます。
それでも我が子のおねしょが続くと、ついついイライラして、いろいろ言いたくなってしまいます。
「『おもらしをしてると小学校に行かれないよ』とか言う必要はないんです。お父さんお母さんに知ってほしいのは、おねしょをした本人がいちばんショックだということ。お子さんもガミガミと怒られたら隠したくもなりますよね。かといって、オーバーに励ます必要はなくて、『あ、しちゃったね』って普通に接してあげるのがいいと思います。」
「お布団を汚されたことで怒りにのぼせてしまうと、おねしょをした我が子がどんな顔をしているのか気づけないんですね。冷静でいると『あ、寂しそうな顔をしているな』『悔しそうな顔をしているな』ということに気づくことができて、『悔しかったね』って共感できるんです。だから親は面倒がらずに、少しでも冷静でいられるような環境を作ることが大切です。その上でお子さんの様子を見てあげてください。」
「このマットレス高かったのに!」などと、無意識のときに起こったことで子どもを責めるのはナンセンス。おねしょをしていちばん落ち込んでいるのは子ども自身なんですよね。「おねしょは必ずするもの」ということを肝に銘じ、おねしょをしてもOKな環境を作ることで、親も子も余計なストレスを感じなくて済みそうです。
おねしょがなくならないのはなぜ?
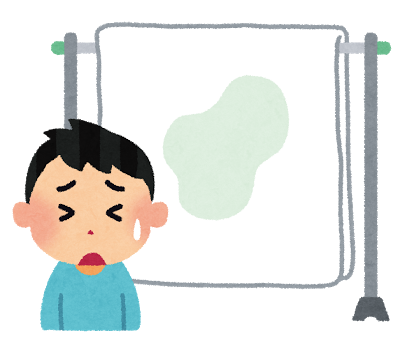 日中のトイレは完璧なのに、夜のおねしょはなくならない。「うちの子はどうして?」と困っているお父さんお母さんは多いと思います。でも、眠っている間のおねしょは、その子自身が原因でないことのほうが多いと珠里さんは言います。
日中のトイレは完璧なのに、夜のおねしょはなくならない。「うちの子はどうして?」と困っているお父さんお母さんは多いと思います。でも、眠っている間のおねしょは、その子自身が原因でないことのほうが多いと珠里さんは言います。「おねしょの原因は、まず、膀胱の機能が未発達だからということが第一です。それから、夜、眠っているときは無意識であるということ。日中は『おしっこしたい』という感覚を感じ取れるようになっていても、睡眠中は無意識ですから。膀胱におしっこが溜まったら自然に出てしまう習慣が残っていますよね。」
日中はおむつがとれていても、夜間のおねしょが心配でしばらくの間、夜は紙おむつを利用しているおうちが多いですよね。そこで、夜のおむつがとれるタイミングを教えてもらいました。
「眠ってから2~3時間後におしっこをしているお子さんは、まだ膀胱が成長しきれていなくて、おしっこを溜められない状態です。そういう子に『夜も紙おむつをはずしましょう』としてしまうと、ストレスになってしまいますので、引き続き紙おむつを利用していいと思います。明け方の4時5時くらいまでおしっこをしていないなら、もう膀胱が成長しているという目安なので、布パンツに替えてもいいと思います。」
膀胱の成長は目で見えないだけに判断が難しいもの。おむつのおしっこチェックラインを見ることで、タイミングを探ってみましょう。
おねしょ期間中に親ができることは?
おねしょを防ぐために、夜中に子どもを起こして「トイレ行く?」の声掛けをする方法もありますが、珠里さんは「あまりおすすめしません」とのこと。「眠っているときに無理やり起こすというのは、睡眠の妨げになるし、お昼に眠くなってしまうし、体調不良の原因にもなりますよね。『どうしても』というのであれば眠りの浅そうなときを見計らって声をかけて、トイレに連れて行くといいと思います。」
明け方におもらしをしてしまうお子さんに対しては、その時間に起こしてトイレに連れて行くのはありだそう。
また、ある程度の年齢になったら親は覚悟を決めて布パンツをはかせるのも手なのだとか。
「5歳、6歳、小学生になっても紙おむつをはいて眠るというのは、股関節を締めつけられるし、あまりいい傾向ではないですね。おねしょが毎日じゃなくて週1度あるかないかだったら、お父さんお母さんが覚悟して布パンツにしてあげるのがいいと思います。そのことによってお子さん自身も意識ができるので、意外とスムーズに布パンツへ移行できることもあるんです。」
おねしょを恐れるあまり、ずるずると紙おむつに頼ってしまいがちですが、おむつはずれには思い切りも必要なんですね。
ふとんやパジャマのおねしょ対策は?
子どもの成長段階において、おねしょは必ずしてしまうもの。だとしたら、おねしょの被害をなるべく少なくするためにはどんなことをすればいいのでしょうか?「まずは、おねしょ専用のお布団で寝かせることですね。防水シーツを敷いて、そこで寝てもらいましょう。それでもパジャマやお布団が濡れてしまうのがどうしてもイヤだというのであれば、布パンツの上に紙おむつをはかせて寝かせる方法もあるし、お子さんが寝入ったら紙おむつをはかせる方法もあります。」
また、親子で相談しながらおねしょ対策を決めるということも大切なのだそう。
「少し大きくなると、紙おむつを絶対にはきたくないというお子さんもいるので、そこはお子さんと話し合って決めるのがいいと思います。うちは、捨てる覚悟で安いお布団を買って、乾かない時期は布団乾燥機を使っていましたね。」
最初からおねしょをしていい状況を作っておけば、親のストレスもぐっと減りそうですね。
怒らずに子どもの気持ちに寄り添って
 それでも我が子のおねしょが続くと、ついついイライラして、いろいろ言いたくなってしまいます。
それでも我が子のおねしょが続くと、ついついイライラして、いろいろ言いたくなってしまいます。「『おもらしをしてると小学校に行かれないよ』とか言う必要はないんです。お父さんお母さんに知ってほしいのは、おねしょをした本人がいちばんショックだということ。お子さんもガミガミと怒られたら隠したくもなりますよね。かといって、オーバーに励ます必要はなくて、『あ、しちゃったね』って普通に接してあげるのがいいと思います。」
「お布団を汚されたことで怒りにのぼせてしまうと、おねしょをした我が子がどんな顔をしているのか気づけないんですね。冷静でいると『あ、寂しそうな顔をしているな』『悔しそうな顔をしているな』ということに気づくことができて、『悔しかったね』って共感できるんです。だから親は面倒がらずに、少しでも冷静でいられるような環境を作ることが大切です。その上でお子さんの様子を見てあげてください。」
「このマットレス高かったのに!」などと、無意識のときに起こったことで子どもを責めるのはナンセンス。おねしょをしていちばん落ち込んでいるのは子ども自身なんですよね。「おねしょは必ずするもの」ということを肝に銘じ、おねしょをしてもOKな環境を作ることで、親も子も余計なストレスを感じなくて済みそうです。







