音楽的才能は人生を豊にしてくれる宝物。のびのびと音楽を聴き、歌い、演奏ができる。そんな能力を身につけられたら素敵ですよね。そのために乳幼児期からできることはあるのでしょうか? 1歳からの幼児クラスを持つヤマハ音楽振興会の須山秀さんにお話をうかがいました。
人気の子どもの習い事をチェック!
身体の発達に合わせて音楽を楽しもう
子どもの音楽教育は「適期」に行うことが大切という須山さん。特に幼児期は心身ともに発達段階であるので、その時期に応じた方法で行う必要があるそう。
1歳〜3歳の乳幼児は耳づくりを重点的に
「一般的に音楽教育というと楽譜を読むところから始まるのですが、1歳から3歳までの小さな子どもには難しいですね。また楽器を演奏するにもまだ手が小さくてうまくいきません。一方で赤ちゃんの耳は、大人並に発達しているものです。ですからヤマハ音楽教室の幼児向けクラスでは、全ての音楽教育の基礎となる耳づくりに重点を置いています」
子どもの音感を育てていくためには、まずは音をキャッチする良質な耳づくりから。
発達に合わせたプログラムで能力を伸ばす
その後子どもの発達にともなって、4,5歳では、音楽を聴く→歌う→弾く→楽譜を読むという過程の中で音感を付けていく、というのがヤマハの音楽教育の考え方だそう。そうやって身体的にも精神的にも、適当な時期に、伸び盛りの能力を伸ばしてあげることで、将来音楽の総合的な力が身につくとのこと。
1歳から3歳までの、お家でできる音楽体験
できないことを強いられると、子どもはストレスを感じてしまうもの。年齢に応じた音楽の楽しみ方を意識すれば、抵抗なく音楽に親しめそうです。須山さんに、年齢にマッチした音楽の楽しみ方を教えてもらったので、参考にしてくださいね。
1歳児に最適な音楽体験
「いとまき」や「とんとんとんとんひげじいさん」などおなじみの遊び歌を、歌を聴いたり動画などを見ながら親が一緒に歌い、赤ちゃんの手をとって手遊びをしてあげましょう。
2歳児に最適な音楽体験
動きを真似ることもできるようになるので、上にあげたような遊び歌を、今度は親子で向かい合って手遊びしながら音楽を楽しみましょう。
3歳児に最適な音楽体験
喜怒哀楽が育ってくる頃なので、遊び歌や童謡を一緒に歌いながら、歌詞について親子で話し合ったりして、意味を味わいながら楽しみましょう。
「ご家庭での音楽教育が実践できる遊び歌やリズム遊びの動画が、ヤマハ音楽教室のウェブページに掲載されていますので、活用してください」と須山さん。さっそくチャレンジしてみましょう!
ヤマハ音楽教室ではどのように音楽にふれあっているの?
「ヤマハでは、1歳〜3歳は、音楽を通して感性や情緒を育む『ぷっぷるくらぶ』で、親子で音楽を楽しみます。3歳(年少以上)になると、『おんがくなかよしコース』で、徐々に鍵盤に慣れていきます。特に4・5歳は音感がどんどん育まれる時期。この時期の子どもたちを対象とした『幼児科』では、拍子、リズム、強弱、何調など音楽のいろいろな要素を聴き分けたり、楽器の演奏レパートリーを増やしたりするなかで音感をつけていきます」
音感が急成長するのは4・5歳の時期なのですね。その時期にスムーズに音楽経験を重ねるためにも、1、2歳から親子の楽しい音楽体験を大切にしたいですね。
耳づくりは0歳から始まっている?!
ところで、親が歌うことに自信が無いと、「遺伝するのでは?」と心配になってしまうのですが……。幼児期から音楽に親しむことで、音楽が苦手にならずに済むのでしょうか? 赤ちゃんのうちから大人並みに耳が発達しているとなると、1歳よりもっと小さなうちから、できることもありそうですが…。
「歌が苦手な方はピッチ、つまり音の高低を合わせられないのです。だから皆で歌っているときに、ズレてきてしまったりするんですね。なぜそうなってしまうのかは諸説ありますが、基本的に赤ちゃんは話し声などの音を聞いて、そこにピッチを合わせることで音感を身につけるそうです。ですから、幼児期の音楽教育も、音楽をしっかり聴いてそのピッチを真似するという繰り返しの練習が効果的なのです」

日常的に聴き、真似することで子どもの音感が養われるので、赤ちゃんの頃から話し声も含めた音の環境を整えることが大切。お母さんが赤ちゃんに話しかけるときの、抑揚や高低をはっきりつけて、ゆっくりと話すマザリーズと呼ばれる話し方が言葉やメロディーの認識に影響し、赤ちゃんの音感を養うのに大きな役割を果たすという説もあるそう。
抑揚をつけて赤ちゃんに話しかけるなど、昔から行っていることには意味があるのですね。遊び歌などの音楽アクティビティーに加えて、乳幼児期の子どもに語りかける際は、真似しやすいピッチの明瞭な発声を意識したいものです。
以下にマザリーズの特徴をあげておきますので、特に言葉を習得する前の赤ちゃんの居るご家庭では、参考にしてみてくださいね。
<マザリーズMothereseの音響特徴>
- 発話の声全体が高い(音声の基本周波数平均値の上昇)
- 抑揚が大きい(基本周波数の変化範囲の拡大)
- ゆっくり話す(発話速度の低下)
- 相手の反応を待つように間をとる(潜時の変化範囲の拡大)
- 同じ言葉を繰り返す(繰り返しの多用)
引用:
ヤマハ音楽研究所 情報Webサイト「ON-KEN SCOPE」 志村洋子「赤ちゃんと音楽 —赤ちゃんの聴取と表出を探る—」総合的な音感の基礎となる聴く力。親子で楽しみながら、良い耳づくりをしてあげたいですね。
人気の子どもの習い事をチェック!
「いこーよ」習い事特集では、人気の子どもの習い事を紹介! 水泳・英会話・ピアノなど、人気習い事ランキングやかかる費用、始める年齢の目安や体験イベント検索まで、まとめてチェックしましょう。
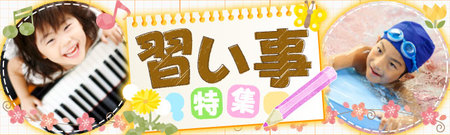 子どもの習い事特集2018
子どもの習い事特集2018






