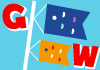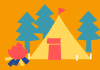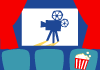家事に育児に仕事に慌ただしく生活する「働くママの1日」に密着する人気企画第2弾! 今回は、ほぼ"ワンオペ"で2人の子どもを育てながら、「いこーよ」編集部で働くママの1日に密着しました!
家事の時短技から子育ての工夫まで、フルタイムで働きながらも家庭をうまく回して充実した生活を送るコツを探ります。
【第1弾】夕食準備15分&毎日子どもを20時に寝かせる時短技フルタイム勤務×ワンオペ育児ママの一日

家族構成:Aさん(29歳)、夫(34歳)、長女(4歳)、長男(2歳)の4人家族
今回紹介するのは、「いこーよ」で子育てやおでかけに関する記事を多く担当している女性編集者のAさん。2016年4月にアクトインディに入社、2017年8月からは正社員として週5日フルタイムで働いています。
2歳と4歳というまだ手のかかる子どもを育てるAさんですが、家事や育児は基本的に1人でこなしているそうです。
一体どんな工夫をしているのか、Aさんの平日のスケジュールをチェックしてみましょう。
出社日のタイムスケジュール
4:00 起床、夫のお弁当を作る
4:30 夕飯の下ごしらえをしながら朝食を済ませる
※耐熱容器に食材をカット&下味をつけた状態にしておく。
【注目ポイント!】

家事の中で「料理」が一番好きではないというAさん。一日に何度も食事の準備をするのが嫌なので、キッチンに立つ時間を朝の時間に凝縮。3食分(朝食、お弁当、夕食)の準備を一気に済ませます。
5:00 勤務開始
※リモート勤務を利用して、子どもたちが起きる前の時間を勤務時間に充てています。
早朝の時間帯は、記事の執筆や原稿チェックなど、一人で集中したい作業を優先的にこなします。
7:30 子どもたちを起こして、朝食を食べさせ、登園準備をする
※この間に食器洗い機に洗い物を入れる、炊飯器を帰宅時間に合わせてセット、さらに自分の身支度をする。
8:30 子どもたちを保育園に送る
10:00 出社
週4日はオフィスへ出社。社内では、ミーティングなどコミュニケーションが必要な業務を優先に行う。
14:00 ランチタイム

※ランチタイムをあえて遅めに設定することで、夕食代わりに。ダイエットにもなるうえ、家族が夕食を食べてる間に、家事の時間も確保でき一石二鳥!
17:00 退社
18:30 子どもたちを保育園へ迎えに行く
19:00 帰宅
帰宅と同時に保育園から持ち帰った洗濯物を洗い、夕食準備をする。
【注目ポイント!】
この間、子どもたちは翌日の準備(保育園の持ち物など)がしっかりできれば、自由に遊んでOKというルールに。「やることさえやれば好きに遊べる」ので、ダラダラせず自発的に準備をしてくれます。

ちなみに、自由に遊んでいいと言っても、毎回部屋が散らかるのは困るもの。そこで、子どもたちが大好きな折り紙や色鉛筆、ハサミ、セロテープ、シールなどをリビングのすぐ手が届く場所に置いています。時間のない平日の夜にたくさんおもちゃを出されることを少しだけ予防しています。
19:40 夕食
※本人は夜食べず、この間に洗濯物を干す。子どもたちとの会話も大切にするため、1日の出来事を聞いたりしながら家事を済ませる。
20:00 夫と長男がお風呂に入る
※この間に、食器を洗い、部屋を片付ける。
20:20 長女と入浴
お風呂はお嬢さんとゆっくり話ができる大切な時間とのこと。4歳児の恋バナを聞いたり、週末の予定をたてたり…「ガールズトーク」を楽しんでいるそうです。
21:00〜22:00 就寝準備
子どもの歯磨きをして、寝かしつけ(子どもたちが1冊ずつ絵本を読む)。子どもと一緒に就寝。
「寝かしつけよう!」と思うと、なかなか眠ってくれない子どもにイライラしてしまうので、「子どもと一緒に寝る」のが一番とのこと。また、「寝かしつけグッズ」も効果的だそうです。
寝かしつけいらず! 我が家のお助け便利グッズ★ほぼすべての家事・育児をAさんが行っていますが、一体どんな工夫をしているのか、日々の生活の中で意識しているコツを教えてもらいました。
平日のバタバタをのりきる「家事&育児のコツ」
動線を徹底的に意識!

水回りなど家の中で使用頻度の高い場所は、動線を徹底的に意識して物を配置しています。調味料は全て開け閉めしやすい容器に詰め替えて、すぐ手の届く場所へ。詰め替え作業は一見大変そうですが、これを一度しておくことで日常の生活が格段に楽になるそうです。
また、台拭きの代わりにキッチンペーパーを愛用。濡れた場所はキッチンペーパーですぐに拭き取ります。カビなどの原因になる水分を事前に拭き取っておけば、掃除が楽になりますね。キッチンペーパーはそのまま捨てられるうえ、衛生的なのも魅力です。
子どもを戦力に!

子どもがやりたがる「お手伝い」は、積極的にやらせているとのこと。一分一秒でも惜しい平日の夜は、「自分でやった方が早いけど…」と思いがち。ですが、そこはグッと我慢し「家族のために何かをして役立った」という経験を重ねることで、子どもの自己肯定感を育めますね。
「ゲーム感覚」で子どもを動かす
平日のタイムスケジュールは、「子どもをいかにスムーズに動かせるか」がカギ。とはいえ、子どもにとって大人のように時間を意識して行動するのは難しいもの。そこでAさんは、生活の中に「ゲーム」を取り入れることで、子どもが自発的に動くような仕掛けを作っているそうです。
たとえば、お風呂上がりに早くパジャマを着てほしいのに子どもが裸で走り回っていた場合、「早く着替えなさい」と普通に言っても子どもは聞きません。そんなときは、家族で早着替えの競争をスタート。実況中継をすると夢中で着替えるそうです(笑)

また、自分の身支度もゲーム感覚で行えるように「お支度ボード」を活用。「着替え」「お風呂」「トイレ」「歯磨き」など、各生活項目をクリアすればマグネットを引っくり返す仕組みで、マグネットの裏側には子どもが好きなキャラクターとママからのメッセージがプリントされています。マグネットを裏返しにしていく達成感が味わえるので、子どもが自発的に身支度できるようになりますね。
100均で簡単DIY! 「お支度ボード」の作り方♪「お片付け」のハードルを下げる
Aさんが日常生活の中で一番困っているというのが、「子どものおもちゃですぐに部屋が散らかること」だそう。「お片付け」の苦手な子どもたちが、自分で遊んだおもちゃをきちんと片付けられるように、とにかく「お片付けのハードルを下げる」ことを意識しているとか。

まず、リビングや寝室など各部屋に散らかったおもちゃを”とりあえず”入れる「とりあえずBOX」を配置。おもちゃを所定の位置まで片付けに行くのが大変なときは、一時的に全てここに入れればOK! まとめて突っ込むだけなので、お片付けのハードルがだいぶ下がります。
あとは、時間があるタイミングで「とりあえずBOX」を子ども部屋に持って行き、親子で一緒にお片付けをします。床に物が散らばっている状態がなくなるだけでも、ママのストレスが削減されますね。
さらに、子ども目線で「お片付けがしやすい」収納を考えることも大切とのこと。Aさんの家では、子ども部屋だけは頻繁に模様替えをしているそう。

子ども部屋の収納は、成長にあわせて都度見直し。子どもが小さい頃はざっくりとした収納で、大きくなるにつれてジャンルごとに細かく収納できるよう工夫しているそうです。
遊びたいおもちゃが入った箱だけを取り出して遊んで、片付けるときは箱ごと元に戻すだけ。これならお片付けも楽ですね。
子ども目線の「収納」とは!?
さらに、絵本の収納は箱に入れるのがオススメだそう。小さな子どもにとって「棚に本を立てて並べる」という行為はなかなか難しいもの。子どもがお片付けの最中にパタパタと倒れてしまう絵本に悪戦苦闘している姿を見てこれに気が付き、箱に入れて収納するスタイルへと変更。上から背表紙が覗き込めるので、子どもが本を選びやすいのもメリットですね。
家族の笑顔が一番!
さまざまな工夫をして家事や育児を一人でこなしているAさんですが、どんなことに気をつけて生活しているのでしょうか? 普段の生活や子育ての中で大切にしていることを教えてもらいました。
Q1. 日常生活で大切にしていること・心がけていることはどんなことですか?
生活の中で心がけていることは、何事も「完璧を求めすぎない」ことです。復職当初は「働いているからと言って手抜きはしたくない!」と、食事を全て手作りして、毎日掃除をして…と頑張りすぎていました。当然、無理のある生活が続くので、自分の余裕のなさから子どもたちに強くあたってしまうことも…。
ある日、娘の「ママに笑ってほしいから、ちゃんと◯◯する!」といった発言を聞いてハッとしました。子どもにそんなことを思わせてしまうくらいピリピリした生活を送っていたことに気が付き、正直かなり落ち込みました。
そこからは「多少家が汚くても死にはしない!」「栄養のある食事は給食で食べてるはず!」という風に、全てを一人で完璧にこなそうという考えを改めました。
Q2.具体的にどのようなことを変えましたか?

食事は基本メインのおかずだけを作り、コンビニやスーパーで買える副菜をプラス。仕事を家に持ち帰ることも多いので、時間がないときは保育園帰りにそのまま外で食事を済ませたり、お弁当などを買って帰ることも多々あります。
また、日常的にはまだ利用していませんが、年末の大掃除は代行サービスを利用しました。普段はあまり一緒にいられない子どもたちとせっかく長く一緒に過ごせるお休みを大掃除で潰したくなかったので、代行サービスを利用して本当に良かったと思いました。
今では、自分以外でもできることは、どんどん外注するようにしています。その分、ママである自分にしかできないこと(子どもとのスキンシップを増やしてたっぷりと愛情を伝えるなど)に注力するようにしています。多少お金がかかったとしても、家族が毎日笑顔でいるための必要経費だと思えるようになりました。
「家事代行サービス」の気になる料金は…!?Q3.休日はどのように過ごしていますか?
平日は帰宅後に作業することも多いので、子どもたちにあまり構ってあげられないことも。その引け目もあり、週末はとことん子どもたちに尽くしています(笑)。子どもたちも週末のおでかけを楽しみにしているので、「次のお休みは◯◯に行けるから頑張ろう!」などと声かけをして平日を一緒に乗り切れます。
週末の朝に「ゆっくり寝てたいな…」と思うこともたまにありますが、寝ているよりも子どもたちと楽しい時間を過ごすことの方がじつは体力回復になるんです。楽しそうにしている子どもたちを見ると「また月曜日から頑張ろう♪」と、自分の活力もチャージされます。
Q4.2人の子どもの育児をするうえで注意していることはありますか?

下の子よりも我慢させることが多い娘とは、意識的に2人だけの時間を作るようにしています。パパがお休みの日に下の子をパパに任せて、娘と2人でお出かけするなどして、娘が一人っ子気分を堪能できる「ママ独占デー」を設けています。普段どこかに行って疲れたとしても、下の子がいるとなかなか抱っこしてあげられないお姉ちゃんをその日はたくさん抱っこして、思いっきり甘えさせています。
仕事と家事、育児を両立しながら、日々の暮らしを楽しむヒントが満載でしたね。ぜひ参考にしてみましょう。