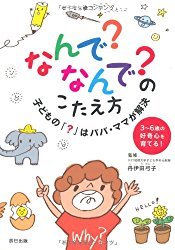子どもの「なんで?」「どうして?」は、飽くなき好奇心の産物。いこーよの読者アンケートで得られた回答の中から、数多くの親が経験している「ベスト・オブ・あるある質問」4つがこちら。小学校で34年間教師をしていた丹伊田(にいだ)弓子先生に、大人は子どもの問いにどう答えたらよいかを指南いただきました。
質問1:赤ちゃんはどうやって生まれてくるの?

ダントツで多かったのがこの質問。コウノトリ頼み? 苦し紛れ? あなたはどう答えますか?
読者の回答例
子「どうして赤ちゃんは出来るの?」→親「それは神様の飼っているコウノトリが運んで来るんだよ」(アンパンマンさん/2歳女の子のママ)
子「赤ちゃんってどうやって出てくるの?」→親「なんかお腹の下のほうから…」と言いながら違う話題に変える。(さぁちんさん/6際、3歳男の子のママ)
子「赤ちゃんがほしい!」→親「神様からのおくりものだからくるかもしれないしきてくれないかもしれないけど、待ってみようね」(レインガ−さん/6歳、2歳男の子のママ)
丹伊田先生より
どんな内容の質問でも、まず、子どもが不思議を発見したことを評価してあげたいですね。「へー、そんなこと考えるなんてすごい!」「こんな小さいうちに気づいたなんて!」というように。
その上で、
親は子どもと一緒に考え、学ぶ姿勢が肝心。必ずしも「正しい答え」を示してあげなくてもよいのです。
人間がどのように誕生するか— 子ども自身が存在する意味を知ろうとする究極の質問です。これに対しては、そのものズバリを伝えるというより、子どもの心をケアしながら話し進めていきたいもの。
「仲良しのお父さんとお母さんが、子どもが生まれてほしいと願って、新しい命をいただくのよ」といった親の考えをまず伝え、犬や馬、ヤギなど動物の出産に関する絵本を一緒に読んで「人間も同じだよ」と伝えてもいいと思います。
質問2:信号は緑なのに、なんで「あお」っていうの?

答えられそうで正確には答えられない——そんな時も、青くならなくてだいじょうぶです。
読者の回答例
子「信号の色、青くないよ、緑でしょ?」→親「…。」(こうちゃんママ/4歳男の子のママ)
丹伊田先生より
信号の色は世界共通。その意味も世界共通です。英語で青信号は「グリーンライト」。日本でも信号が普及した当初(昭和5年)は「緑」と呼んだようです。
日本語は、緑の葉を「青々とした」と表現したり、「青物市場」「青葉」「青菜」といった呼び方をしたりする独特の言葉の文化があります。その影響でいつの間にか「青信号」と呼ばれるようになった、というのが一つの説です。
もう一つは、当時の新聞が信号を「青」と書いてから「青信号」という呼び方が普及したという説もあります。
こうした説に対して、「本当かな?」と子どもと一緒に調べていく姿勢が大切。
親はわからなければ、「わからない」と伝えてもいいと思います。その上で、どうしたらわかるようになるのか、その方法や道筋を子どもに示してあげること。子どもは、何でも教えてくれる大人より一緒に学んでくれる大人が好きなのです。
質問3:なんで夏は暑いの?

類似した質問として、「なぜ夜になるの?」「どうして地球は丸いのにここは平らなの?」などなどがありました。
読者の回答例
子「なんで夏は暑いの?」→親「お日様がお当番の回数が多い季節だからだよ」(K・Kさん/5歳男の子のママ)
子「太陽は、夜になると月になるの?」→親「地球が回るからだよ」→子「どうして回るの?」→親「回らないで太陽だけの人は夜ねれないし、月だけの人はずっと寝てないといけないよ」(ひなそらさん/7歳、2歳女の子のママ)
丹伊田先生より
こうした科学の問題は、子どもの「なぜ?」が次の「なぜ」を生むような答え方をしたいものです。
例えば、「お日様の光や熱をたくさん受ける季節とそうでない季節があって、夏はお日様の光や熱をたくさん受けるから暑いのよ」→「なんでお日様の光を受ける季節と受けない季節があるの?」→「地球は、自分で回転しながら(自転)太陽の周りを回っているの(公転)。
地球は、少し傾きながら太陽の周りを回るから、太陽に近い時や遠い時があって、その時期ごとに暑かったり寒かったりするのよ」というように。
また、科学=真実と思われていますが、かつて天動説が地動説へとくつがえされたように絶対的なものではありません。「くつがえることもある」「解明されていないこともある」と教えることは子どもの興味関心をさらに引き出すでしょう。博物館や水族館、プラネタリウムなどに出掛けて親子で「真実」を追求していきましょう。
質問4:サンタさんは本当にいるの?

「子どもの夢を壊してはならない」という妙な使命感に、アタフタする親も多いようです。
読者の回答例
「サンタクロースは本物?」と聞かれ「どう思う?」と逆に質問した。(ストモさん/女の子のママ)
子「サンタクロースって、プレゼントくれるけど、家に勝手に入ってくるから泥棒だよね?」→親「不法侵入する良い人!」→子「確かに…」。納得しちゃった。(最新型のお母さん/8歳男の子、5歳女の子のママ)
子「サンタさんは本当はいなくて、パパがプレゼントを買ってるの?」→親「キミが疑った時点でサンタさんはもう来なくなると思うよ」(WHさん/7歳男の子のパパ)
丹伊田先生より
100年以上前、アメリカの6歳の女の子が「サンタクロースっているんでしょうか?」と新聞に投書した有名な話があります。その新聞では、「愛とか思いやりとかいたわりとかがちゃんとあるように、サンタクロースもちゃんといます」と答えています。そう、
サンタクロースについての疑問は、「答えのわからないことがある」「たくさん答えがあるものがある」と子どもに伝えるよき題材です。
私自身ならわが子にこう伝えるでしょう。
「本当に誰かを信じたり愛したり憧れたりする気持ちは、私を幸せにしてくれる。
サンタを見た人に出会ったことはないけれど、子どもの頃からサンタは思うだけで私を幸せにしてくれた。きっとサンタは誰でも幸せにするほど大きくて、大きすぎて見えないんじゃないかな。(子どもの体を包んで)ほら、あなたもこうするとママが見えないでしょ。目に見えないけれど心で感じる本当のことってあると思う。今はそう思っている」と。
サンタクロースに関する絵本もたくさん出ています。先に挙げた新聞の社説も絵本になっているので、一緒に読んでみてもいいですね。
まとめ:子どもと一緒に学ぶワクワク感を
いかがでしたか?
親は、「正しく答えよう」と身構える必要はなく、一緒に考え、調べ、学ぶ姿勢が大切なのだと丹伊田先生は教えてくれました。
「子どもの質問に対して、『ここまでは知っている。ここから先は一緒に学ぼうね』『私はこう思う』と親子の対話のきっかけにしてください。Aの答えはBと簡単に答えて終わりではなく、子どもに夢を持たせてあげる対話にしたいですね。
探究心の強い子どものそばには、往々にして探究心の強い大人がいます。大人も一緒に学ぶ楽しさを味わってください。」
じつは、子どもの質問攻めにやや閉口していた筆者ですが、なんだか両手を広げて質問を歓迎したくなりました。子どもの「なんで?」「どうして?」の嵐は時としてうるさく感じてしまうものですが、質問は興味や関心を広げ、親子のコミュニケーションのきっかけにもなるものと前向きに捉えていきたいですね。